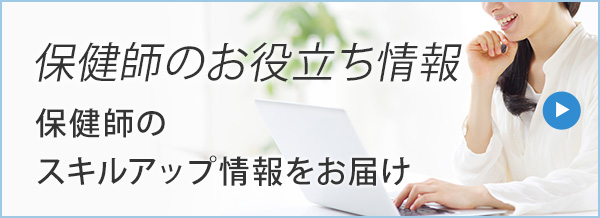【保健師】仕事内容・役割現場で役立つ!産業保健師のストレスチェック業務を徹底解説
公開日:2015年12月25日
更新日:2025年08月08日

こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。
「産業保健師がストレスチェックでどのような役割を担うか知りたい!」
「ストレスチェック業務の進め方や具体的な対応がイメージできない......」
「保健師のキャリアアップにストレスチェックのスキルはつながるの?」
このような悩みを持つ人のために、アポプラス保健師のライターチームが疑問を解決する記事を執筆しました。
2015年12月より、一定数以上の従業員のいる職場ではストレスチェックの実施が義務化されました。ストレスチェックの運営には、保健師を含む専門家が携わることが定められています。そのため、産業保健師として働く場合、実施者や事務従事者として業務に携わる可能性が高いといえます。
本記事を読めば、ストレスチェックのやり方や必要なスキルを知ることができるため、自信を持って実務に挑めるようになるはずです。ストレスチェック業務は、メンタルヘルス対応や職場環境改善の知見など幅広いスキルを得ることにつながるため、将来的なキャリアアップにも役立つでしょう。例えば、メンタルヘルス対策に特化したポジションへの転職や労働衛生コンサルタントなどの専門資格取得の土台作りにもつながります。
ストレスチェック業務に関心がある方、自分のスキルを活かせる職場を探したい方は、保健師専門の転職支援サービスもあわせて活用してみてください。ぜひ最後まで記事を読んでみてください。
目次
- ・ストレスチェック制度とは
- ・産業保健師のストレスチェックにおける役割
- ・産業保健師によるストレスチェックの実施手順
- ・産業保健師としてストレスチェックに関わるメリット
- ・ストレスチェック対応に必要なスキル・知識
- ・ストレスチェックの結果を活用した職場環境改善方法と事例
- ・ストレスチェック実施における注意点
- ・産業保健師のストレスチェックに関するよくある質問
- ・保健師のストレスチェック業務をキャリアの武器に変える
ストレスチェック制度とは

2015年12月より、従業員が50人以上の事業所では、年に1回ストレスチェックを実施することが義務付けられました。ここでは、ストレスチェック制度について目的や実施フローなどを具体的に紹介します。
ストレスチェック制度の概要と目的
ストレスチェックとは、働く人の抱えるストレスの状況を調べる検査のことです。定期的にストレス状況を確認することで、個人のメンタルヘルス不調を防いだり、職場環境の改善につなげたりする効果があります。
ストレスチェックの実施フローと関係者
職場でストレスチェックを実施する際、産業保健師は実施者もしくは実施事務従事者として関与することが多いでしょう。
事業者は実施者とともにストレスチェックの準備や計画を行いますが、従業員から回収された質問票を分析するのは実施者です。結果は実施者から本人へ直接通知されるため、従業員の同意なく、事業者が結果を知ることはありません。
ただし、職場ごとに集計した集団分析の結果は、職場環境の改善に役立てるため実施者から事業者へ通知されます。
産業保健師のストレスチェックにおける役割

職場でストレスチェックが行われる場合、産業保健師は実施者として運営に関わることが多いと考えられます。ここでは、産業保健師のストレスチェックにおける役割を紹介します。
実施者としての役割と責任
ストレスチェックの運営に携わる主な関係者は、実施者と実施事務従事者の2種類にわけられます。労働安全衛生規則では、実施者になれる者を医師・保健師・看護師・精神保健福祉士などの有資格者に限定しています。なお、看護師や精神保健福祉士については3年以上の実務経験または研修の受講が必要です。
一方、実施者を補佐する実施事務従事者については、特別な資格は不要ですが人事権を持たない人物であることが求められます。そのため、人事権を持たない人事部の職員や、総務部門などの従業員が選ばれる場合もあります。
高ストレス者対応のポイント
ストレスチェックにより高ストレス者と判定された従業員は、医師との面談指導を受けることが推奨されています。産業保健師は従業員のプライバシーを守りつつ面談がスムーズに進むよう、医師をサポートしましょう。
また、高ストレス者が医師との面談を希望しない場合には、産業保健師が代わりに相談を行ったり、セルフケアの方法を指導したりすることもあるでしょう。
集団分析と職場環境改善のサポート
ストレスチェックの結果を集団単位で分析して、職場としての傾向を事業所へ伝える役割を産業保健師は担うことが多いです。また、集団分析の傾向を踏まえて職場環境の改善につなげられるよう、産業医や人事担当者などの関係者のサポートも行います。
産業保健師によるストレスチェックの実施手順
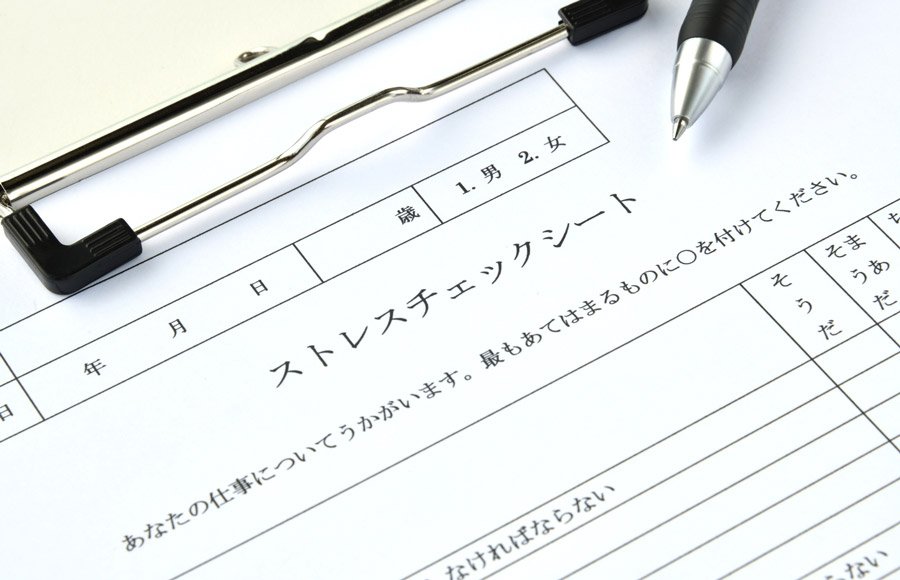
ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした制度です。産業保健師は、実施者や事務従事者としてこの制度の運用に関わることが多く、手順全体を把握しておくことが重要です。
ここでは、ストレスチェックの実施手順を簡単に紹介します。
以下はストレスチェックを実施する際の主なステップです。
| ステップ | 概要 |
|---|---|
| ステップ1 | 実施方針の決定、衛生委員会での協議、実施者・事務従事者の選任など「準備と計画」の段階です。 |
| ステップ2 | 質問票(ストレスチェックシート)の配布・回収を行う「受検の実施」の段階です。オンラインや紙媒体での対応方法を選びます。 |
| ステップ3 | 回答内容をもとに高ストレス者を選定し、必要に応じて医師の面接指導を実施します。 |
| ステップ4 | 結果を本人に通知し、個人情報の適切な管理と活用方法を定める「事後対応」の段階です。 |
【ステップ1】ストレスチェックの準備と計画
ストレスチェックの実施前に、まず事業者が実施方針を決定し、衛生委員会などで具体的な実施体制や実施方法を定める必要があります。ストレスチェックの実施者と実施事務従事者の選定はこの段階で行われます。
【ステップ2】ストレスチェックシートの配布と回収方法
検査は基本的に実施者などが作成した質問票に対し、従業員が回答する形式で行われます。ストレスチェックシートの配布と回収方法は、事業所や従業員の働き方に合った方法を選びましょう。マークシートやオンライン受検など、従業員が参加しやすい方法を取ると回答率が高まります。
【ステップ3】高ストレス者の選定基準と医師による面接指導の流れ
従業員から質問票を回収したら、高ストレス者を選定します。厚生労働省のストレスチェック制度実施マニュアルによると、各質問への回答内容に応じて点数を割り振り、その合計点数が一定水準を超えた場合に高ストレス者と判定する方法が一般的です。メンタルヘルス不調を防ぐため、高ストレス者には医師との面接指導を推奨します。
【ステップ4】結果の通知と個人情報の適切な管理方法
ストレスチェックの結果は個人情報にあたるため、適切に管理できる体制をあらかじめ整えておくことが大切です。結果は実施者から従業員一人ひとりに直接通知します。本人の同意なく、事業者を含む第三者が取得したり閲覧したりすることのないよう注意する必要があります。
産業保健師としてストレスチェックに関わるメリット

産業保健師としてストレスチェックに関わるメリットは、主に以下の4点です。
- メンタルヘルス対応スキルが高まる
- 組織との連携力・マネジメントスキルの習得
- 企業に必要とされる専門職としての信頼性向上
- 人事・経営に近い立場で働けるやりがい
メンタルヘルス不調者への対応スキルが高まることは、ストレスチェックに関わる大きなメリットです。さまざまな職場においてメンタルヘルス不調に悩む従業員は少なくないため、メンタルヘルス対応スキルの高い産業保健師は活躍の機会が広がるからです。
特にストレスチェック後の面談対応や、高ストレス者への支援の中では、「適切に話を聴く力」「医師や人事と連携し、必要な支援につなげる判断力」など、実践的で応用力の高いスキルが養われます。こうしたスキルは、ストレスチェック以外の面談業務や復職支援、職場改善提案などにも活かせるため、産業保健師としての専門性を一段と高めることができます。
また、ストレスチェックの運営を通して企業の人事担当者や経営層と近い立場で働くことでやりがいを感じられる、知識や視野が広がるのも大きな魅力です。
弊社エグゼクティブアドバイザーとして活躍している久保さやかさんを講師にお迎えし、ストレスチェックの概要や集団分析結果の活用方法について、わかりやすく解説していただきました。
ストレスチェック対応に必要なスキル・知識
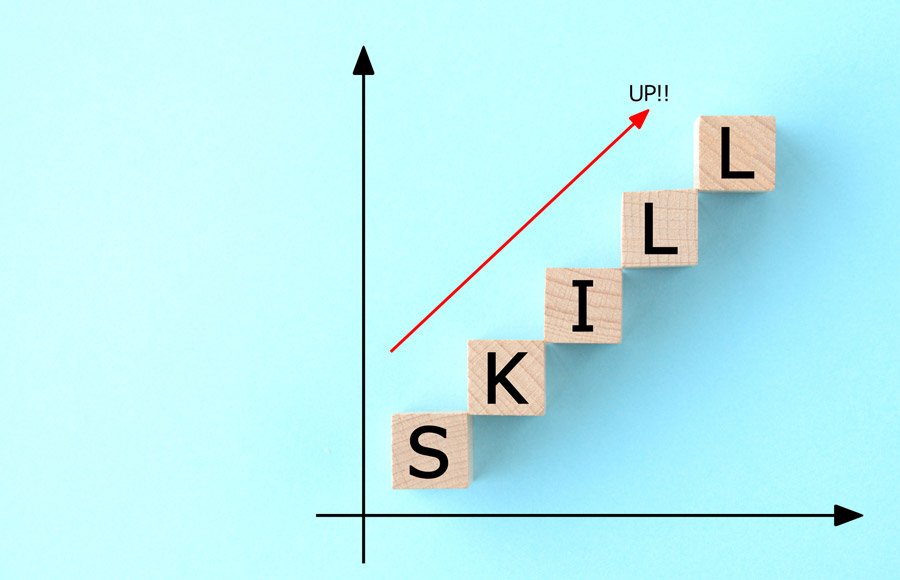
産業保健師としてストレスチェックに対応する際、必要なスキルや知識を紹介します。
制度対応・運用に関する知識
産業保健師としてストレスチェックに関わる方は、事前に制度対応や運用に関する知識を身につけておくことが大切です。制度の概要や目的の理解には、厚生労働省のホームページなどの情報を参考にしてみてください。
また、実際の運用方法や従業員が回答する質問票は職場によって異なります。職場の産業医や人事担当者などに確認しておきましょう。
面談・フォロー対応
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判断された方のうち本人が希望する場合は医師との面談指導が受けられます。ただし、本人が面談指導を希望しない場合は代替手段としてセルフケアを行うことも可能です。
その際は保健師がセルフケアの方法を指導するといった形で、従業員をフォローする場面があるでしょう。
組織改善・集団分析に関する知識と視点
ストレスチェックの目的の一つは、結果を集団分析し、よりよい職場作りに役立てることです。
ストレスチェックの実施者として、保健師には組織改善や集団分析に関する知識や視点が求められます。特に組織改善においては、組織構造やマネジメント、コミュニケーションなどに関する知識を身につけておくとよいでしょう。
関連資格や研修への参加
産業保健師として従業員をサポートするスキルを伸ばすためには、関連資格や研修への参加を通して日々新しい知識を身に付けることが大切です。たとえば産業カウンセラーなどの資格の取得は、ストレスチェックに関連して従業員からメンタルヘルスに関する相談を受ける機会の多い産業保健師に役立ちます。
従業員をサポートする際に役立つスキルや資格についてより詳しく知りたい方は、次の記事も参考にしてみてください。
産業保健師のスキルアップに役立つ資格4選を紹介し、キャリアにつながる選び方や、資格を取得するメリットも解説します。

ストレスチェックの結果を活用した職場環境改善方法と事例

ストレスチェック制度の目的の一つは、実施結果を活用して職場環境を改善し、従業員のメンタルヘルス不調を防ぐことです。しかし、実際にはストレスチェックの結果の活用ができていない職場は少なくありません。
ここでは、ストレスチェックの結果を職場環境改善につなげる方法を紹介します。
職場環境改善の進め方と保健師の役割
ストレスチェックの結果を職場環境改善につなげる際に、保健師が果たす役割には以下のようなものがあります。
- 衛生委員会での共有
- 施策の提案
- 現場との連携 など
衛生委員会では、保健師としての専門知識や経験に基づいた、職場環境改善につながる情報共有や施策の提案が期待されています。
職場環境改善の進め方は、次のようなプロセスが基本です。
- ストレスチェック結果の集計・分析部署単位での傾向を把握し、改善が必要なポイントを明確にします。
- 分析結果の衛生委員会での共有保健師が専門的な視点から結果を読み解き、改善の方向性やリスクを提言します。
- 具体的な施策の提案と計画立案必要に応じて産業医や人事と連携し、優先度の高い施策から順に計画を立てます。
- 現場との連携による施策の実施・モニタリング保健師が現場とコミュニケーションを取りながら施策を支援し、継続的な改善につなげます。
保健師は、こうしたプロセス全体に関与しながら、専門知識や中立的な立場を活かして職場全体の健康づくりを推進します。また、従業員の中には、人事担当者や産業医には話しにくいことも保健師には相談しやすいと感じる方がいます。話しやすい雰囲気を作り、従業員からの声を直接聞いて、産業医などの他の専門職に情報を伝えて連携していくことも、保健師の大切な役割といえるでしょう。
改善施策の具体例
ストレスチェックを実施しても職場環境の改善につなげられない職場では、以下のような問題が起きていることがあります。
- 職場環境改善の実施について事業者の理解を得られない
- 高ストレス者からの面接指導の申し出が少ない
これらの課題に対しては次のような施策が効果的です。
【課題1】職場環境改善の実施について事業者の理解が得られない
経営層に対し、職場環境改善によって期待される効果(従業員のパフォーマンス向上、離職率の低下、企業イメージの向上など)を丁寧に説明する機会を設けることが重要です。
- 職場環境改善の効果(業績向上・離職防止など)を経営層に分かりやすく説明する
- 衛生委員会とは別に「経営層向けの説明会」や「勉強会」を開催する
- 健康経営・働き方改革など経営層が関心を持ちやすいテーマと関連づけて伝える
【課題2】高ストレス者からの面接指導の申し出が少ない
高ストレス者に対しては、面接指導の重要性や利用メリットを周知するとともに、心理的なハードルを下げる工夫が必要です。
- 面接指導の重要性やメリットを従業員に周知する
- 気軽に相談できるオンライン相談窓口を設置する
- 情報の取扱い(誰に共有されるか、プライバシーは守られるか)を明確に説明することで安心感を与える
ストレスチェック実施における注意点

50人以上の従業員がいる職場では、ストレスチェックの実施が義務化されていますが、従業員一人ひとりの参加は任意とされています。しかし、従業員のストレスチェック受検率が低い場合、集団分析を行っても適切な結果が得られない可能性があります。
できる限り多くの従業員がストレスチェックに参加するよう、保健師を含む関係者で連携して対策を取るとよいでしょう。具体的には繁忙期を避けて実施する、従業員や管理職に対してストレスチェックを受けるメリットを周知するといった方法があります。
なお、ストレスチェックについて案内する外国語版の資料を厚生労働省では公開しています。職場に外国人の従業員がいて、外国語の資料が必要な場合には、厚生労働省の「外国語版の職業性ストレス簡易調査票等」のページを確認してみましょう。
産業保健師のストレスチェックに関するよくある質問

職場で実施されるストレスチェックにおいて、産業保健師は重要な役割を持っています。ここでは、産業保健師のストレスチェックに関して、よくある質問とその答えを3つ紹介します。
Q:保健師はストレスチェックの実施者になれますか?保健師は実施者または実施事務従事者としてストレスチェックに関与することが認められています。多くの場合、産業医や人事担当者と連携しながら、実施計画の立案から結果の管理、面接指導のサポートまで幅広く担当します。職場の状況に応じて、専門知識を活かしながら円滑な実施を支える重要な役割を担います。
Q:50人未満の職場でもストレスチェックは必要ですか?義務ではありませんが、実施が推奨されています。
現在適用されている労働安全衛生法では、ストレスチェックの実施が義務づけられているのは「常時使用する労働者が50人以上いる事業場」のみです。そのため、50人未満の職場には法的な義務はありません。ただし、従業員50人未満の職場であってもメンタルヘルス対策として、努力義務として実施が推奨されています。職場の状況に応じて簡易な形でも導入を検討すると良いでしょう。
Q:メンタルヘルス対応に不安がある場合は?支援体制が整った職場を選びましょう。
メンタルヘルス不調者への対応に不安がある場合は、自主学習や実務経験を通じてスキルを高めつつ、人事や産業医と連携できる体制が整った職場を選ぶことが重要です。一人で抱え込まず、相談しやすい環境に身を置くことが、安心して働くためのポイントです。
保健師のストレスチェック業務をキャリアの武器に変える

ここまで、ストレスチェックの制度や保健師の役割について詳しく見てきました。実際に現場で業務にあたる中で、「もっと専門性を活かした働き方がしたい」「やりがいを感じられる職場で長く働きたい」と感じる方もいるかもしれません。
ストレスチェック業務は、保健師の専門性が特に発揮される分野です。メンタルヘルス支援や職場環境改善に関わる中で、ご自身のキャリアや働き方について考えるきっかけになることもあるでしょう。
「今の職場が合わない」「もっと自分らしく働きたい」と感じたときは、産業保健師としてのキャリアを検討することも一つの選択です。職場環境改善やメンタルヘルス支援に深く関わる仕事は、保健師としての価値をさらに高めるチャンスになります。
そんなキャリアを目指す方には、保健師に特化した転職支援サービス「アポプラス保健師」がおすすめです。長く働ける職場を探したい、市場価値の高いスキルを身につけたいなど、保健師のキャリア形成にお悩みの方はぜひアポプラス保健師にご相談ください。
保健師専門の転職サポート!32年の実績!
転職サポートに登録(無料)【新着】お役立ちブログ
- 2025年11月17日 産業保健師は未経験からでも始められる!キャリアチェンジ完全ガイド
- 2025年11月17日 【2025年最新版】保健師・看護師の平均年収を徹底解説|年代・地域別の違いと収入アップ術
- 2025年11月17日 保健師はフルリモート勤務できる?求人の実情と応募条件・働き方を解説
- 2025年10月20日 産業保健師の転職はエージェント活用で差がつく!未経験でも安心の理由と賢い使い方
- 2025年08月28日 【30代で産業保健師に】未経験からでも目指せる?転職を成功に導く準備とポイント