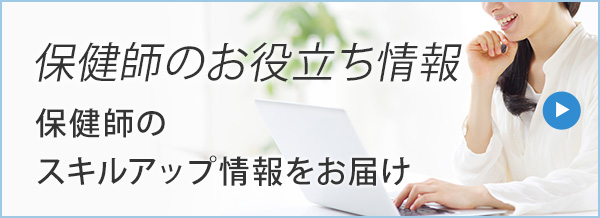【保健師】仕事内容・役割【保健師向け】出産後の保健師訪問とは?「必要ない」「迷惑」と思われる3つの理由や円滑にするポイント
公開日:2016年02月25日
更新日:2025年03月24日

こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。
「保健師の訪問って具体的にどのようなことをするの?」
「新生児訪問や赤ちゃん訪問って必要なの?」
「保健師訪問を受ける側の気持ちを知りたい!」
このような悩みを持つ人のために、保健師転職のアポプラス保健師のライターチームが疑問を解決する記事を執筆しました。
保健師の大切な業務の一つに、出産後の家庭への訪問があります。慣れない子育てに戸惑っているかもしれない親御さんのもとへ伺い、必要なサポートを提供することを目的とした訪問です。
ただし、場合によっては親御さんから「必要ない」「迷惑」と思われてしまうおそれもあるでしょう。そのように思われてしまう理由や、保健師による訪問を円滑に進めるためのポイントについて解説します。
目次
- ・保健師の訪問の目的とは?
- ・【新生児訪問】新生児がいる家に保健師が訪問
- ・【赤ちゃん訪問】4カ月内の乳児がいる家に保健師が訪問
- ・保健師の訪問が「必要ない」「迷惑」と思われる理由3選
- ・【クレーム・危険を防止】保健師の訪問を円滑におこなう4つのポイント
- ・妊婦がいる家に対して保健師が訪問する場合も
- ・まとめ|母子サポートのため保健師訪問を円滑に進めましょう
保健師の訪問の目的とは?

出産後、お母さんは2〜3時間おきに授乳したり頻繁にオムツ替えをしたりして、赤ちゃんとの新しい生活を始めることになります。幸せを感じる瞬間も多いですが、これまでとまったく違う生活で睡眠時間も取れず、肉体的にも精神的にも疲れてしまうケースがあるでしょう。
保健師による訪問の目的は、そのようなお母さんと赤ちゃんのサポートです。産後間もないお母さんの心身のケアや子育ての相談、赤ちゃんの発育状態の確認などをおこないます。
出産後から28日目までに訪問する「新生児訪問」と、生後4カ月までに訪問する「赤ちゃん訪問」があり、それぞれ母子保健法や児童福祉法で定められている事業です。対象家庭に目的をわかりやすく説明し、地域ぐるみで子育てを進められる環境を目指しましょう。
【新生児訪問】新生児がいる家に保健師が訪問

「新生児訪問」は、生まれたばかりの新生児がいる家庭に保健師が訪問して、必要なサポートをおこなう制度です。正式には「新生児訪問指導事業」と言い、保健師以外に助産師や看護師が訪問するケースもあります。
訪問は無料で、強制ではありません。出産直後の落ち着かない時期のため、訪問を断る家庭もありますが、赤ちゃんだけでなくお母さんのケアのためにも、できるだけ訪問を受け入れてもらえるよう進める必要があります。
新生児訪問のタイミングはいつ?
新生児訪問のタイミングは、出産から28日以内です。里帰りしての出産の場合には、出産から60日以内に延長されます。具体的な訪問日時は、訪問家庭の状況や要望に合わせて設定します。
新生児訪問の内容と所要時間は?
新生児訪問の内容は、お母さんの心身のケアや赤ちゃんの健康サポートです。お母さんの健康状態を確認し、授乳やその他の不安があれば相談に乗ります。赤ちゃんとの生活で困っていることがあれば、そのアドバイスもします。
また、赤ちゃんの体重測定をして、発育状態や栄養状態を確認することも大切です。乳幼児健康診査や予防接種の説明もして、不安が大きいようであれば相談窓口を紹介します。所要時間は家庭によってそれぞれ異なりますが、30分程度から1時間半ほどのケースが多いです。
新生児訪問の流れは?
出産後、母子健康手帳とともに交付された「出生通知票(出生連絡票)」が役所に提出されます。通知票に基づいて役所から新生児のいる家庭に連絡をして、訪問の日時を調整する形が一般的です。
おおよその所要時間を伝え、忙しいようであれば何時までに訪問を終えたほうがよいかについても確認しておきましょう。なお、里帰り出産の場合は、里帰り先で新生児訪問を受けているケースもあります。訪問日時を調整する際には、里帰り先での新生児訪問についても確認してみてください。
【赤ちゃん訪問】4カ月内の乳児がいる家に保健師が訪問

「赤ちゃん訪問」は、生後4カ月までの乳児がいる家庭へ訪問する制度です。正式には「乳児家庭全戸訪問事業」と言い、自治体によっては「こんにちは赤ちゃん訪問」といった名称で呼んでいるケースもあります。
この訪問は、生後4カ月までの赤ちゃんがいるすべての家庭が対象です。保健師だけでなく、助産師や地域の民生委員、子育て経験のある方などが無料で訪問します。
赤ちゃん訪問のタイミングはいつ?
赤ちゃん訪問のタイミングは、生後4カ月以内です。生後28日以内には新生児訪問があるため、実際には生まれてから2〜4カ月の間におこなわれます。自治体によっては、二つの訪問をまとめておこなうケースもあります。
赤ちゃん訪問の内容と所要時間は?
赤ちゃん訪問の際も、新生児訪問と同じように母子ともに健康で困っていることはないかなどを確認します。お母さんは、育児の疲れや悩みが出てきている頃かもしれません。お話を伺い、必要があればアドバイスし、子育て支援の窓口を紹介することもあります。
子育てしている環境のチェックも大切です。もしも支援が必要だと感じた場合には、早期に適切なサポートをおこないます。
子育てが始まると、お母さんは周囲との交流が少なくなり、孤立してしまうケースもあります。そのような問題に早めに気づくことが、赤ちゃん訪問の目的の一つです。孤立状態の改善は、子どもの虐待防止にもつながります。
所要時間は自治体や家庭ごと異なりますが、30分から1時間程度です。
赤ちゃん訪問の流れは?
出産後に提出された「出生通知表(連絡票)」に基づいて、赤ちゃん訪問の訪問員が各家庭に連絡します。その後、日程を決めて訪問する流れです。
同じ地域に住んでいる訪問員が訪問するケースが多いため、お母さんにとっては地域とつながるチャンスかもしれません。その地域でおこなわれていて子どもと一緒に参加できるようなイベントなど、地域密着の情報を提供することもあります。
保健師の訪問が「必要ない」「迷惑」と思われる理由3選

保健師の訪問は、母子の健康にとって有益なことが多いでしょう。ただ、場合によっては訪問先から「必要ない」「迷惑」と思われてしまうケースもあるようです。
なぜそう思われてしまうのか、その理由を考えてみましょう。
プライバシーの侵害だと感じる
赤ちゃんが産まれたあとに半ば強制的に保健師の訪問を受け、家庭環境や育児の状態などをチェックされてしまうため、プライバシーの侵害だと感じる方もいるようです。たしかに、子育ての悩みなどを伺ううえで、プライベートな内容にまで踏み込んでしまうケースが多いかもしれません。
しかし、保健師をはじめとする訪問員には守秘義務があり、プライバシー厳守を基本としています。それについて理解してもらえるよう、きちんと説明したうえで訪問するようにしてください。
忙しいときに対応するのがつらい
保健師による訪問がおこなわれるのは、産後の新しい生活が始まったばかりの時期です。子育てはもちろん、その他さまざまな事情で忙しい家庭も多いでしょう。家の中が片付いていなかったり、お母さん自身がメイクをして人に会う気分になれなかったりといったケースも考えられます。
そのため、訪問されても対応する余裕がない、対応するのがつらいと思う方もいるのです。家の中が散らかっていても構わないことや、産後は片付けの時間がない家庭も多いと伝えて、少しでもつらさを軽減できるようにしてみてください。
必要性を感じていない
出産後もとくに困ったことがなく、周囲に相談できる人もいて、順調に子育てができているケースもあります。そのようなケースでは、保健師による訪問の必要性を感じてもらえないかもしれません。
訪問は玄関先で簡単にお話を伺うだけと伝え、赤ちゃんに会わせてもらえるようにしましょう。訪問の必要性が伝わっていない段階では、相手方から迷惑と感じられてしまう可能性がある点は、知っておくようにしてください。
【クレーム・危険を防止】保健師の訪問を円滑におこなう4つのポイント

保健師による訪問は、生まれてきた赤ちゃんが健やかに成長していくようサポートするために重要です。だからこそ、訪問が円滑に進むよう、次のようなポイントに気をつけましょう。
訪問先からクレームを受けないよう、さらに訪問時に危険な状況に陥らないよう、これらを守るようにしてください。信頼関係をしっかり築きながら、新生児訪問や赤ちゃん訪問を進めることが何よりも大切です。
事前連絡を徹底して訪問の必要性を説明する
訪問前の事前連絡の際には、訪問の必要性を丁寧に説明するようにしてください。出産前に比べて産後は忙しく、赤ちゃんの夜泣きで生活リズムも乱れているかもしれません。「訪問されても対応する余裕がない」と感じている家庭もあるでしょう。
そうした点を理解し、訪問を拒否された場合には「なぜ訪問が必要なのか」をわかりやすい言葉で説明するようにしてください。産後の家庭に寄り添って、話を進めましょう。
住民の状況に配慮しながら柔軟に対応する
家庭ごとに、生活のリズムは違います。夫婦と赤ちゃんの3人暮らしなのか、祖父母と同居しているのかなどによっても、生活環境が異なります。訪問されても問題ない時間帯や、訪問されては困る時間帯などもあるでしょう。
そのような住民の状況に配慮しながら、訪問のタイミングを柔軟に検討してください。訪問を断られないようにするためにも、無理のない範囲で訪問先の家庭の事情に合わせることが大切です。
聞くことや伝えることを明確にして負担をかけない
訪問時に聞きたい・伝えたい内容は事前にリストアップしておくなど、明確にしておきましょう。内容をシンプルにまとめ、端的に話すようにしてください。
相手方に過度な負担をかけないような心配りも大切で、たとえばお茶などをすすめられても基本的には遠慮するほうがよいでしょう。訪問前に、お茶などは一切気を使う必要がないことを伝えてもよいかもしれません。
ただし、訪問先ごとに臨機応変な対応が重要です。相談や悩みを打ち明けたいと考えているお母さんであれば、じっくり話を聞いてあげてください。
訪問時に危険があることも視野にいれておく
ごくまれではあるものの、訪問時に危険があることも否定できません。出産後の家庭への訪問といっても、赤の他人の家への訪問です。もしものときのことを視野にいれ、訪問してください。
いつ、どの家庭を訪問するかについては、きちんと報告しておいたほうがよいでしょう。
妊婦がいる家に対して保健師が訪問する場合も

新生児訪問や赤ちゃん訪問と並んで、妊娠中から出産、育児の時期の母子をサポートする事業として「妊婦訪問支援事業」があります。妊娠中の方が不安なく出産して子どもを育てていけるよう、妊婦のいる家庭に保健師や助産師が訪問サポートする制度です。
若年の妊婦や経済的に不安がある、パートナーや家庭の状況から育児が困難になると推測されるといった妊婦は、とくに重点的にサポートします。自治体によって進め方は異なりますが、すべての妊婦が安全に出産・育児できるようにするためのものです。
相談に乗ってアドバイスをしたり、健診を受診するように促したりします。必要に応じて、専門機関を紹介するケースもあります。
まとめ|母子サポートのため保健師訪問を円滑に進めましょう
出産後の家庭を訪問する新生児訪問や赤ちゃん訪問、妊娠中の家庭を訪問する妊婦訪問は、母子ともに健やかに暮らしていくための強力なサポートになるでしょう。その中で、保健師は重要な役割を持っています。
保健師による訪問をスムーズに進めて、「必要ない」「迷惑」と思われないように、必要なタイミングで必要なサポートを届けられるようにしましょう。訪問先との信頼関係を築いて、妊婦が安心して出産・育児できる環境を目指してください。
保健師専門の転職サポート!32年の実績!
転職サポートに登録(無料)【新着】お役立ちブログ
- 2026年01月15日 主婦から保健師になるには?資格取得の4つのルートと学費・年齢の現実を解説
- 2026年01月15日 【2026最新】看護師のスキルアップ資格15選|働きながら取れる?難易度・費用・年収を全比較
- 2026年01月15日 【2026年最新】保健師の就職先10選|行政・企業・病院の違いと選び方
- 2026年01月15日 保健師と看護師の違いとは?|向いている人・年収・働き方・転職ルートを解説
- 2026年01月15日 【例文テンプレ付き】保健師の志望動機完全ガイド|市町村・企業・学校別の受かる書き方