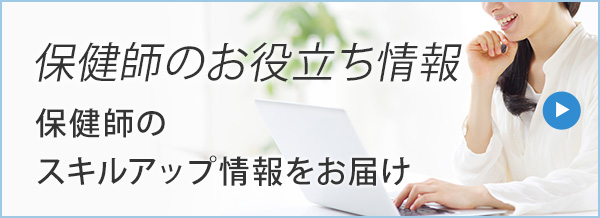【保健師】業界情報保健師が知っておきたい!保健師助産師看護師法について
公開日:2015年10月26日

こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。
保健師助産師看護師法は、昭和23年(1948年)7月30日に制定されました。
第一章総則の第一条には、"この法律は、保健師、助産師及び、看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。" とされています。
「保健師」「助産師」「看護師」は、それぞれ異なる資格ですが、"厚生労働大臣の免許を必要とする国家資格である"という点については同じです。
ただし、「保健師」と「助産師」は「看護師」の資格をもっていなければ取得することはできません。
つまり、どの資格を取るにしても、まず「看護師」の資格取得は絶対条件になるということです。
では、具体的に3つの資格の違いをみていきましょう。
看護師とは
~疾病または疾患を負う人や産婦のお世話、診療を補助します~
保健師助産師看護師法の第一章総則の第五条には、
"この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診察の補助を行うことを業とする者。"とあります。
傷病者(傷病又は疾患を負っている人)、じよく婦(出産後間もなくの女性、産婦)のお世話や診療の補助を行う人ということです。
看護師のほかに「准看護師」という資格もあります。
保健師助産師看護師法の第一章総則の第六条には、
"この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師、又は看護師の
指示を受けて、前条(保健師助産師看護師法の第一条総則の第五条)に規定することを行うことを業とする者。"とあります。
「看護師」が国家資格であるのに対し、「准看護師」は都道府県知事免許となります。
(取得した都道府県内に限定されず、日本全国で有効な免許です)
保健師とは
~健康な生活を送れるようにサポート、集団検診や健康相談を行います~
保健師助産師看護師法の第一章総則の第二条には、"この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。"とあります。
保健指導とは、学校や保健所などで集団検診や健康相談を行うことです。
つまり、看護師との大きな違いは、対象となる人が傷病者だけではなく、健康な人も入ることです。あらゆる人が健康な生活を送れるようにサポートする仕事といってもよいでしょう。
助産師とは
~助産、そして産前産後、新生児の保健指導までを行います~
保健師助産師看護師法の第一条総則の第三条には、"この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。"とあります。
「看護師」「保健師」との大きな違いのひとつとして、女性にしか取ることのできない資格ということになります。
(ただし日本の場合であり、海外には男性の助産師もいます)
さらに、看護師がみる対象者がじよく婦に限られているのに対し、助産師の仕事は、妊婦、新生児の保健指導にまで広がります。
看護職の法律である「保健師助産師看護師法」
「看護師」「保健師」「助産師」は、業務内容がそれぞれ異なる国家資格なのです
「看護師」「保健師」「助産師」という3つの職種は総称して「看護職」と呼ばれています。
しかし、それぞれが異なる資格であり、異なる業務をするということをご理解いただけたでしょうか?看護する対象となる人が異なったり、現場で行えることが異なったりと、さまざまです。
どんな仕事をしたいかによって取得すべき資格は変わりますが、看護職を目指す人にとっての初めの第一歩は「看護師」です。
さらに別の業務を行いたい人が目指すのが、それぞれ「保健師」「助産師」という資格の取得になります。
つまり、保健師助産師看護師法とは、看護職を目指す人にとって重要な法令といえるのです。
3つの資格について簡単にお話ししたところで、次に「保健師助産師看護師法」の保健師にスポットをあてて、さらに詳しくお話しします。
保健師の仕事
保健指導の内容って?
保健指導の内容は、保健師が勤務する場所によっても変わってきます。
保健所や保健センターに勤める行政保健師の場合は、妊産婦に対して、乳幼児に対して、お年寄りに対して、障害をもつ方に対して、などさまざまな対象者に保健指導を行います。
企業などに勤める産業保健師の場合は、その企業の社員たちの心と体の健康を維持するべく、保健指導を行います。
学校などに勤める学校保健師の場合は、その学校の学生及び職員に対して行うことになります。
基本的に保健師が携わるのは「予防医学」の分野であり、病気や怪我人を対象とする看護師とは、仕事の内容が根本的に違うものとなります。
看護師免許ももつ保健師
医療行為の有無は?
保健師も看護師も医師ではありませんから、医師や歯科医師の指示なく医療行為をすることは認められていません。ただし臨時応急手当てなどは、その限りではありません。
これは保健師助産師看護師法の第四章第三十七条で、以下のように定められています。
"保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。
ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。"
場面にあわせ臨機応変に対応することは、保健師にも看護師にも求められているということでしょう。
保健師の守秘義務
それは保健師でなくなった後も続きます
保健師助産師看護師法の第四章第四十二条の二により"保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。" と定められています。
保健師を含め、医療に携わる看護師や准看護師は、患者さんを含む一般の方のプライベートな情報について知りうる場面があります。当然のことではありますが、その秘密を漏らしてはいけないという守秘義務があることを忘れてはいけません。
また、保健師の資格を失った後も同様であることを、覚えておきましょう。
最後に復習!看護師国家試験過去問より
「保健師助産師看護師法」に関わるクエスチョン
こちらをご覧いただいている方の中には、看護師の資格をとったのはずいぶん昔になる・・という保健師さんや、これから保健師を目指すという方もいらっしゃることでしょう。
正直「保健師助産師看護師法」の詳しい内容は覚えてないわ!という方も、改めて確認しておきたい問題をいくつかご紹介します。
第94回「看護師が業務上行うことができないのはどれか」
- 1.
静脈内注射の実施
- 2.
心マッサージの実施
- 3.
創部の消毒
- 4.
薬剤の処方
答え:4
第99回「看護師の行動で適切なのはどれか」
- 1.
看護計画を立案するために診療録を自宅へ持ち帰った
- 2.
看護記録に誤りを見つけたので修正液を使って修正した
- 3.
患者の友人から病状を聞かれたので答えられないと説明した
- 4.
患者の氏名が記載された看護サマリーを院外の研修で配布した
答え:3
第103回「保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか」
- 1.
看護研究
- 2.
記録の保存
- 3.
秘密の保持
- 4.
関係機関との連携
答え:3
看護師・保健師のみなさんなら簡単な問題ばかりだったでしょうか。
保健師を続けるうえで「保健師助産師看護師法」は知っておくべき法律です。
時に改正させることもありますので、そういったときは「何が改正されたのか」を把握するなど、意識しておきたいものです。
保健師専門の転職サポート!32年の実績!
転職サポートに登録(無料)【新着】お役立ちブログ
- 2026年01月15日 主婦から保健師になるには?資格取得の4つのルートと学費・年齢の現実を解説
- 2026年01月15日 【2026最新】看護師のスキルアップ資格15選|働きながら取れる?難易度・費用・年収を全比較
- 2026年01月15日 【2026年最新】保健師の就職先10選|行政・企業・病院の違いと選び方
- 2026年01月15日 保健師と看護師の違いとは?|向いている人・年収・働き方・転職ルートを解説
- 2026年01月15日 【例文テンプレ付き】保健師の志望動機完全ガイド|市町村・企業・学校別の受かる書き方