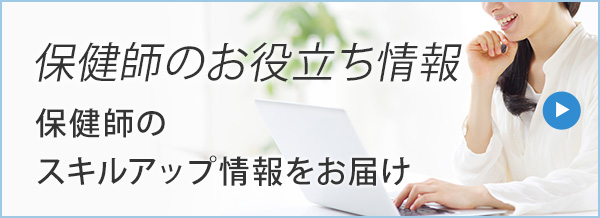【保健師】業界情報現在社会には必須!?産業保健師のメンタルヘルスへの取り組みについて
公開日:2016年01月25日

こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。
ここ数年、職場におけるメンタルヘルスの取り組みが強化されていることは、みなさんご存じのことと思います。
厚生労働省が発表した「労働者のメンタルヘルス関連対策の経緯」によると、昭和63年9月1日に「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を大臣が公示したことが始まりとされています。
その後、平成12年8月9日に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」の策定が始まり、平成18年3月31日には「労働者の心の健康保持増進のための指針」が公示されました。
同年4月1日に「改正労働安全衛生法」を施行、平成23年12月には「労働安全衛生法」の改正案を国会に提出しました。
平成26年6月25日には「改正労働安全衛生法」が公布されるなど、国をあげてメンタルヘルスの取り組みを行ってきました。
現代社会に必須といわれるメンタルヘルスケアは、なぜこのように重要視されているのか?
また産業保健師はどのように取り組んでいけばよいのか?
考えていきたいと思います。
厚生労働省基準局安全衛生部労働衛生課「平成26年職場におけるメンタルヘルス対策の推進について」参照PDF
メンタルヘルス対策の現状
自殺者数や気分障害患者数について
平成10年以降、自殺者数が3万人のラインを超え、うち25%以上が「被雇用者・勤め人」であることがわかっています。
平成24年に自殺者総数はようやく3万人のラインを下回りましたが、平成25年自殺者のうち「被雇用者・勤め人」の割合は26.7%という結果になっています。
また自殺者の中で原因・動機の特定ができたものを調べると11.5%が「勤務問題」となっており、これは「健康問題」に次いで多い理由となっています。
一方うつ病などの気分障害の総患者数は、平成11年が44万人だったのに対し平成14年には71万2千人に増加。
さらに平成17年は92万3千人、平成20年は1,04万1千人となりました。患者を年齢別性別でみると、男女とも40代~50代の壮年期にもっとも数が多くなっています。
平成24年の労働調査では、職場における悩みのトップが「職場の人間関係」で41.3%、次いで「仕事の質」33.1%、「仕事の量」30.3%となっており、人間関係のストレスが病気に大きく関わっているであろうことが予想できます。
実際、精神障害等の労災補償状況は年々増加傾向にあり、平成12年の請求件数が212件だったのに対し、平成25年の請求件数は1409件、認定件数は436件となっています。
このような現状から、現代社会において「メンタルヘルス」の取り組みが重要視されているのです。
メンタルヘルスの取り組み
各事業場での変化は?
実際、事業場でのメンタルヘルス対策への取り組みは、どのような状況になっているのでしょうか。
労働者健康状況調査報告によると、平成14年は取り組んでいると答えた事業場は23.5%、平成19年は33.6%、平成24年は47.2%と徐々に増えてはいますが、まだまだ足りない状況です。
そこで政府は、平成29年までに80%を超えることを目標に掲げています。
取り組まない理由として「必要性を感じない」「専門スタッフがいない」「取り組み方がわからない」という意見があります。
これらを解決するためにも、平成26年12月1日から開始した「ストレスチェック制度」は、重要な役割を果たすのではないでしょうか。
メンタルヘルス国の取り組み
ストレスチェック制度について知っておこう!
厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」ではメンタルヘルスケアの原則的な実施法について、以下のような4つのケアの必要性が書かれています。
- 1)
メンタルヘルスケアの教育研修・情報提供
- 2)
職場環境等の把握と改善
- 3)
メンタルヘルス不調への気づきと対応
- 4)
職場復帰における支援
また平成27年4月15日に公表された「ストレスチェック制度」については、従業員50人以上の事業所を対象に義務付けられ、平成27年12月1日から施行が始まりました。
厚生労働省のホームページでは、導入マニュアルなどがダウンロードできるようになっていますので、産業保健に関わる方はご覧になっておくとよいでしょう。
検査結果については検査を実施した医師・または保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業所に提供することは禁止されています。
この点についても、保健師はきちんと理解をしておく必要があります。
また義務付けされてはいませんが、従業員50人未満の事業場の事業主に対しては、ストレスチェック制度実施促進のための助成金制度もあります。
労働者健康福祉機構又は最寄りの産業保健総合支援センターで問い合わせできますので、こちらについても覚えておいてください。
独立行政法人 労働者健康福祉機構「ストレスチェック実施促進のための助成金」参照![]()
メンタルヘルスの取り組み
産業保健総合支援センターの存在とは?
メンタルヘルスの取り組みを広げるための機関として、独立行政法人労働者健康福祉機構が運営する「産業保健総合支援センター」があるのをご存じでしょうか。
事業主を対象とした企業経営の観点からみた産業保健に関するセミナーや、労働者を対象とした啓発セミナーなどを行っています。
また保健師をはじめ、産業保健に関わるすべての人を対象に、産業保健に関する相談・研修・情報提供などの支援も、原則無料で行っています。
全国47都道府県に配置されていますので、産業保健に関わる保健師の方は相談機関のひとつとして覚えておいてはいかがでしょうか。
メンタルヘルスの取り組み
産業保健師は従業員のよき相談相手に
従業員にとってメンタルヘルスに関する悩みというのは、打ち明けにくいものです。
事業所によっては産業医と保健師が常駐していると思いますが、従業員にとっては産業医への相談はハードルが高く、保健師には気持ちを打ち明けやすいという面があるようです。
つまり保健師はメンタルヘルスケアの専門家であると同時に、従業員にとって話しかけやすい存在であることを自覚しておくことも必要かもしれません。
早期の相談により病気になる前に解決できたり、治療がスムーズに進んだりしますので、「従業員が声をかけやすい環境」を作ることは大事です。
メンタルヘルスケアは産業医・保健師だけでなく、さまざまな人が連携して対応することが求められますが、従業員にとって最初の窓口となり得る保健師の存在は実は重要なのです。
産業保健師として、従業員の心の支えになれるよう日々心がけたいものです。
保健師専門の転職サポート!32年の実績!
転職サポートに登録(無料)【新着】お役立ちブログ
- 2026年02月09日 産業保健師の平均年収はいくら?年代別・勤務先別の目安と年収アップの現実的な方法
- 2026年02月06日 【看護師辞めたい】7つの理由と「辞めるor続ける」の判断基準と対処法も解説
- 2026年02月06日 【保存版】産業保健師のスキルアップに役立つ資格19選|目的別の選び方・費用・難易度も解説
- 2026年02月06日 産業保健師はなぜ大変?しんどさの原因・向き不向き・今すぐできる対処法まで解説
- 2026年02月06日 【保存版】産業保健師の面談スキルアップ術|目的・種類から「対象者の心を開く」実践ノウハウまで