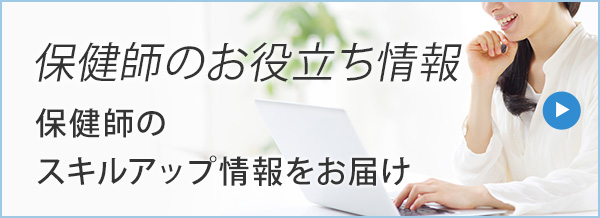【保健師】仕事内容・役割保健指導(健康指導)とは?内容や対象者、特定保健指導との違い
公開日:2024年07月25日

こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。
保健指導は保健師がおこなう業務のひとつで、人々の健康を守り、病気の早期発見・改善を目指すために欠かせない取り組みです。しかし、保健指導の具体的な内容や実施されるシーンをイメージできない方もいるでしょう。なお、保健指導と混同されるものに「特定保健指導」がありますが、実際の内容は大きく異なり、その違いを理解しておくことも欠かせません。
今回は保健指導(健康指導)の概要や実施される内容、おこなわれる場面を紹介します。保健師の仕事に興味がある方や保健師への理解を深めたい方はぜひご覧ください。
目次
保健指導(健康指導)とは

保健指導(健康指導)とは、医療専門家が対象者の健康増進を目的として、あらゆる人に実施するものです。ここでは保健指導の目的や対象者について解説します。なお、場合によっては健康指導とも呼ばれますが、今回は便宜上、本文中では今後、「保健指導」と呼称します。
目的
保健指導を実施する目的は、対象者の健康を守り、かつ問題を早期発見することにあります。具体的には、対象者の健康状態の把握や健康維持のための生活習慣の改善方法の提案、セルフケアの指導などを実施します。
対象者
保健指導の対象者は多岐にわたります。病院を訪れた方や学校の生徒、自治体の住人などさまざまです。そのため、対象者を限定することはありませんが、健康診断等で把握した対象者の健康状態によって「情報提供レベル」「保健推奨レベル」「受診推奨レベル」に指導のレベルを分類するケースが一般的です。
よくあるケースは、企業の健康診断で病院を訪れた際に、結果をもとに保健師をはじめとした専門家から保健指導を受けるというものです。しかし、それ以外にも保健指導をおこなうフィールドはあるため、理解を深めていきましょう。
内容
保健指導の内容は大きくわけて「生活指導」「栄養指導」「運動指導」の3つにわけられます。ここではそれぞれの内容を詳しく解説します。
生活指導
1つ目の生活指導は、対象者の健康上の問題や予防・解決を目的に、生活習慣改善のアドバイスやストレス管理などの指導をおこなうものです。
近年注目を集めている生活習慣病は、自覚症状がないまま進行したり、長期間の生活習慣が起因したりする特徴を持ちます。そのため、病気を発症してから改善をおこなうだけでなく、まだ比較的リスクが低い状態から生活習慣を改善し、予防する必要があります。
具体的には、睡眠や運動の習慣、また食生活におけるネガティブな習慣について対象者に改善方法を提案し、取り組んでもらうことがあげられます。
しかし、「強制」にならないよう、あくまで可能性であることを伝えたうえで、対象者の意思や健康への考え方に配慮したアドバイスが求められます。ただ「治すべき」と指摘するのでなく、快適かつ楽しめるようなプログラムや提案を意識する必要があります。
栄養指導
2つ目の栄養指導では、生活習慣病をはじめとしたさまざまな疾患を未然に防ぐ、また進行を食い止めるために食習慣の評価や栄養摂取量に関する指導をおこないます。対象者の現在の食生活についてヒアリングをおこない、改善すべき点があればアドバイスをおこないます。
この際、アレルギーの観点でも注意をはらう必要があります。場面によっては管理栄養士と連携を取りながら実施することもあります。
運動指導
3つ目の運動指導では、対象者の生活状況や身体活動レベル、趣味や運動への意欲などを考慮し、運動プログラムの作成や実践の指導をおこないます。
生活習慣病を予防するためには、食生活や睡眠など生活の随所で改善が求められます。さらに、日々の生活の中に運動を適切に取り入れることで、メタボリック・シンドロームや加齢に伴う筋力低下など、さまざまなトラブルの予防につなげられます。
近年はテレワークの推進による運動量の低下、そして子どもの運動不足が顕著です。保健師は指導の中で、そうした社会問題を意識しながら適切な指導をおこなう必要があります。
実施者
保健指導の実施者は主に下記の専門家があげられます。
- 医師
- 保健師
- 管理栄養士
- 看護師
- 薬剤師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科医師
- 歯科衛生士 など
医療福祉分野のエキスパートが保健指導を担います。
保健指導の具体例
ここからは保健師が保健指導をおこなう具体的な3つのシーンを紹介します。
- 企業の職場
- 学校など教育機関
- 地域の健康に関する行事
職場の保健指導
職場での保健指導は、健康診断のタイミングだけでなく企業のイベントとして実施されることもあります。近年は従業員のヘルスケアサポートに力をいれ、保健指導により従業員の困りごとを解消し、健康に働けるようサポートをおこなう企業が増加しています。
企業が成長するには、従業員一人ひとりのパフォーマンスを向上させることが不可欠です。保健指導は、従業員の健康をサポートすることで一人ひとりのパフォーマンスを向上させ、企業成長に貢献できます。
学校の保健指導
教育現場における保健指導も重要です。近年は児童生徒の心身における健康問題が多様化し、保護者や教育者、そして医療従事者には柔軟な対応が求められています。その中で、子どもが抱える健康不安が大きくなる前に、保健指導で悪化を防止する取り組みが欠かせません。養護教諭や学校職員と連携し、子どもを守るための保健指導がおこなわれています。
心理的ストレスやいじめ、アレルギー疾患など保健指導の範囲は多岐にわたります。児童生徒は大人と比較してデリケートであることから、実施者にはきめ細かな対応が求められます。
地域の保健指導
地域の方々に対する保健指導もよくある取り組みです。たとえば、自治体が主催する健康診断や、イベント等で参加者の健康相談に乗るといったものが代表的です。対象者は高齢者や若年層などさまざまですが、地域イベントでは「来てくださりありがとうございます」という感謝の気持ちをもって、対象者とかかわる必要があるでしょう。
また、イベントで保健指導をおこなう場合は、病院をはじめとした医療機関と比較して悩みや対象者が抱える事情が多様化する傾向があります。そのため、実施者には柔軟性が求められます。
また、病院と比較して対象者に緊急性がないことが多いため「やってみようかな」と思ってもらえるような提案方法が求められます。
特定保健指導とは
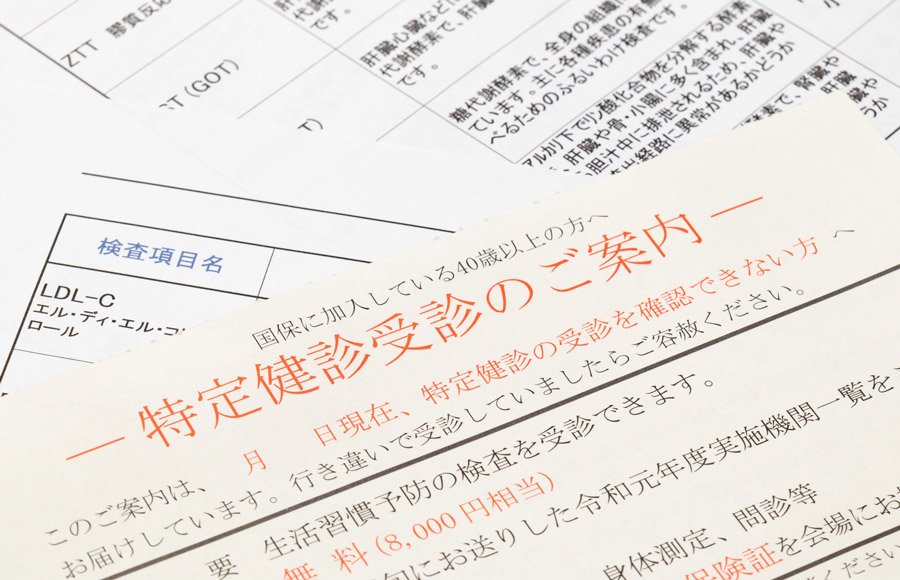
保健指導は実施する場面がさまざまで、対象者も多岐にわたります。しかし、それとは別に対象者が限定される「特定保健指導」というものもあります。ここでは特定保健指導について、概要や対象者を解説します。
目的
特定保健指導は、現代日本における死亡原因の多くを占める、生活習慣病の有病者・予備群を減少させることが目的です。代表的な生活習慣病は下記の通りです。
- 脳卒中
- がん
- 心臓病
- 糖尿病
また、国際的には下記も生活習慣病としてあげられます。
- 慢性閉塞性肺疾患
- 非感染性疾患 など
かつてこれらの病気は「成人病」として扱われていました。40〜60代の働き盛りの方に多く、老化に伴って病気の発生は避けられないものであると捉えられていましたが、検診や聞き取りをおこなう中で、生活習慣を見直すことで予防できるとの認識が強まりました。その結果、特定保健指導という形でサポートをおこなっています。
生活習慣病のリスクについて対象者に理解を促し、食習慣や喫煙・飲酒の頻度を見直すといった生活習慣の適切な改善策を提案します。
具体的には、内臓脂肪型肥満(メタボリック・シンドローム)に着目し、食生活や運動習慣を見直すことがあげられます。
対象者
対象者は40歳以上75歳未満の医療保険加入者が受ける特定健康診査の結果から、腹囲等の数値と血糖、脂質、血圧の数値が一定以上となる項目が見られた方です。なお、リスクの数の組み合わせによって、特定保健指導のレベルを判定し下記のとおり定めます。
- 情報提供レベル
- 動機づけ支援レベル
- 積極的支援レベル
なお、特定保健指導では「動機づけ支援」「積極的支援」の段階での指導をおこないます。しかし、いずれも対象者に対して「べきである」と強制するのでなく日常生活に取り入れやすい方法を提案したり、一緒に取り組んでいく姿勢を見せたりする必要があります。
自身の健康状態に対して懸念点が見られると、誰もが焦りを感じます。しかし、そこで保健師をはじめとした専門家が特定保健指導で寄り添うことで「健康維持をサポートしてもらえる」といった安心感を与えられるでしょう。
参照:政府広報オンライン「生活習慣病の予防と早期発見のために がん検診&特定健診・特定保健指導の受診を!」
内容
特定保健指導の内容は、基本的に対象者との面談を通じて、指導内容や改善策を決めていくものです。しかし、方針は動機づけと積極的支援で少々異なります。具体的には下記のとおりです。
動機づけ支援レベル:対象者の健康状態の自覚と、生活習慣改善のための取り組みの継続が目的。面接や指導を通じて行動計画を策定して実行への動機づけとその実績評価をおこなう。
積極的支援レベル:動機づけ支援と同様、面接や指導を通じて行動計画を策定・実績評価。対象者の主体的な取り組みに資する働きかけを相当な期間、継続する。
※積極支援レベルの方が緊急度が高いことから、長期間支援することになります。
実施者
特定保健指導の実施者は主に下記のとおりです。
- 常勤の医師
- 保健師
- 管理栄養士
- 一定の保健指導の実務経験がある場合は看護師
こちらも保健指導同様に、医療関係のエキスパートが実施します。
特定保健指導の具体例
ここでは特定保健指導の具体例を紹介します。実際におこなう際のイメージに役立てましょう。
動機付け支援の具体例
動機づけ支援の具体例としては、メタボリックシンドロームに該当する対象者に、このままの生活を続けると考えられる疾患の情報を提供し、毎日続けられる運動や食事の取り方について知らせることがあげられます。
対象者に知識を獲得してもらい、すぐに実践できる提案をおこなう必要があります。
積極的支援の具体例
積極支援の具体例としては、年に一度の検診を軸に、改善に向けた対象者の主体的な取り組みと並行して、食事や運動を継続的に支援し、集団教室への参加などを促すことがあります。
積極支援では、より改善に向けて継続的な指導、支援をおこなう必要があります。
まとめ|保健指導は保健師の重要な業務
保健指導は保健師がおこなう業務のひとつです。対象者や実施するシーンが多岐にわたるため、向き合う相手に合わせたアプローチが求められます。指導をおこなう際は、相手の立場や気持ちに寄り添ったていねいな対応が求められます。
保健指導をとおして、対象者の健康意識を改善できたり実際に体調に変化が現れたりした際は達成感を得られる仕事でもあります。「人の健康維持の役に立ちたい」と考える場合は保健師の道を検討するのもよいでしょう。
アポプラス保健師では、保健師を目指す方のサポートをさまざまな形でおこなっています。求人のご案内やキャリアについて知りたい方はぜひ一度、ご相談ください。
保健師専門の転職サポート!32年の実績!
転職サポートに登録(無料)【新着】お役立ちブログ
- 2025年10月20日 産業保健師の転職はエージェント活用で差がつく!未経験でも安心の理由と賢い使い方
- 2025年08月28日 【30代で産業保健師に】未経験からでも目指せる?転職を成功に導く準備とポイント
- 2025年08月28日 保健師の転職はいつがベストな時期?行政・産業保健師のタイミングの違いと成功のコツ
- 2025年08月28日 【保健師PDCA完全ガイド】成功事例と失敗しない改善ポイント
- 2025年08月28日 【体験談あり】看護師から保健師への転職完全ガイド|年収・やりがい・働き方のリアル