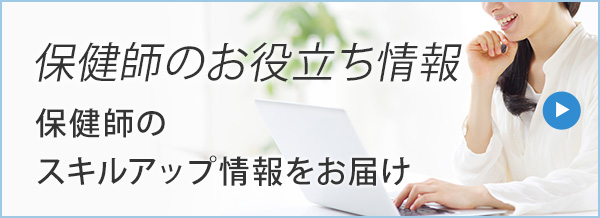【保健師】業界情報保健師助産師看護師法はどんな法律?業務規程や押さえるべき内容を徹底解説
公開日:2014年11月11日
更新日:2024年11月13日
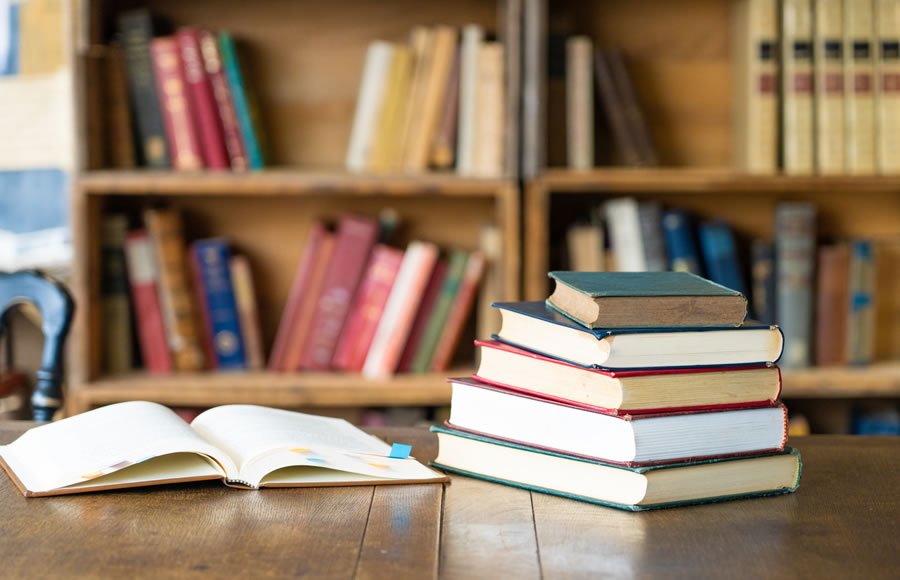
こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。
保健師助産師看護師法とは、保健師・助産師・看護師の資格や業務に関する基本的なルールを定めた法律です。保健師助産師看護師法により、医療従事者は患者に対する安全で質の高いサービスを提供するための指針を得られます。
本記事では、名称独占や業務独占、守秘義務など、保健師や看護師として知っておくべき重要な規定に焦点を当てて、法律の主要なポイントを解説します。
目次
- ・保健師助産師看護師法とは
- ・保健師助産師看護師法で定められた職種ごとの業務
- ・保健師・助産師・看護師・准看護師になるには?
- ・保健師・助産師・看護師資格の欠格事由
- ・保健師助産師看護師法の名称独占・業務独占に関する規定
- ・保健師助産師看護師法における守秘義務と罰則
- ・まとめ|保健師として働くなら保健師助産師看護師法を把握しておこう
保健師助産師看護師法とは
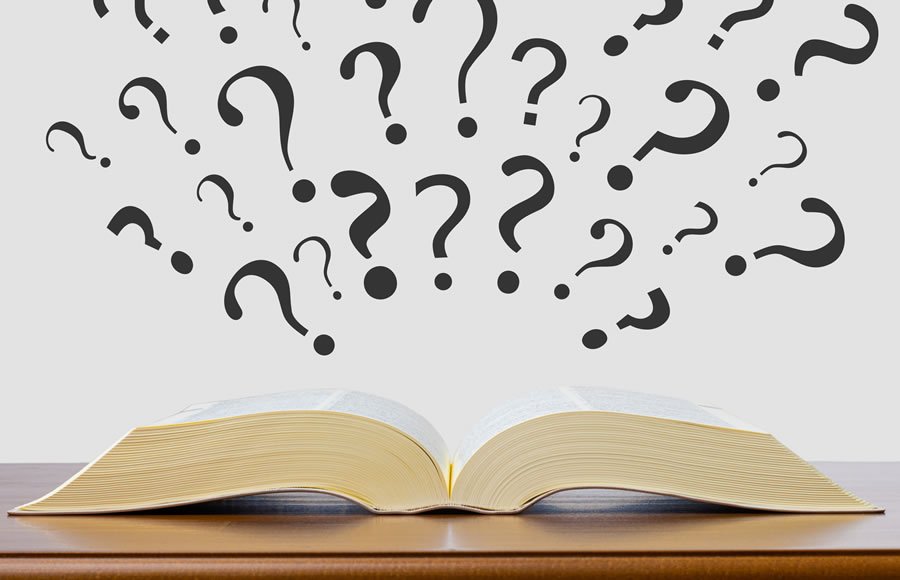
保健師助産師看護師法とは、保健師・助産師・看護師の3つの職業に関する規定を定めた法律です。1948年7月30日に初めて施行され、保健師や助産師、看護師が高い専門性と倫理観を持って業務を遂行できるよう作られました。その結果、国民の医療と公衆衛生の質を向上させる目的があります。
保健師助産師看護師法の第1条には「この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もって医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする」と明記されています。
保健師助産師看護師法で定められた職種ごとの業務

保健師助産師看護師法では、保健師・助産師・看護師・准看護師の4つの職種ごとに、具体的な業務内容が定義されています。法律の定めにより、各職種の役割や責任がはっきりし、医療や公衆衛生の分野でそれぞれが果たすべき役割が整理されています。ここでは、それぞれの職業がどのような業務を担っているのか、詳しく見ていきましょう。
第2条|保健師
第2条では、保健師について次のように定義されています。「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受け、保健師の名称を用いて保健指導に従事することを業とする者を指します。保健師の業務内容は働く場所によっても異なりますが、地域住民・従業員・児童に対する生活指導や環境の調整などです。
たとえば、保健所や市区町村役場では、乳幼児健診や母親学級など母子保健活動や健康づくり事業を企画・実施し、病気の予防や健康管理に関する指導をおこないます。また、高齢の自宅療養者を訪問し、療養に関する相談や指導をおこなうのも業務の一環です。
企業では健康管理部門での勤務が一般的で、社員の健康相談や健康診断結果に基づく保健指導、快適な労働環境作りに寄与します。学校では、養護教諭として児童・生徒、教職員の健康相談や健康診断後の指導をおこない、健康な生活習慣の促進に努めます。
第3条|助産師
第3条において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産・妊婦・じょく婦・新生児の保健指導を業とする女性を指します。助産師の仕事は、健康な妊婦と胎児の誕生を支援し、女性の出産や産前・産後の健康問題にかかわることです。
具体的な業務内容は以下の通りです。
- 妊娠時の保健指導
- 出産時の介助
- 新生児のケアや生活援助
- 保護者への育児相談や指導
- 思春期や更年期の性に関する相談
- 不妊治療をおこなう夫婦への相談
助産師は病院や医院での勤務の他、助産院の開業もおこなえます。なお、現在、助産師免許の取得は女性に限定されています。
第5条|看護師
第5条では、「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者またはじょく婦に対する療養上の世話や診療の補助をおこなうことを業とする者を指します。看護師は、病院や自宅において病気や怪我で療養している人が安心して療養生活を送れるよう支援し、健康回復を促すのが主な仕事です。
診療の補助・生活上の援助・家族に対しての介護法指導・医療関係者との調整をおこない、不安のない療養生活になるようにサポートします。
第6条|准看護師
第6条において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師または看護師の指示を受けて前条に規定する業務をおこなうことを業とする者を指します。
業務内容は看護師とほぼ同様ですが、准看護師は独自の判断で看護業務をおこなえず、必ず医師や看護師からの指示を受けなければなりません。准看護師は看護師に対して指示が出せない点も異なるため注意が必要です。
保健師・助産師・看護師・准看護師になるには?

保健師・助産師・看護師・准看護師の職業に就くためには、国家資格の取得などが必要です。資格を取得するためのルートや過程は異なりますが、いずれも専門的な教育と試験を受ける必要があります。ここでは、それぞれの職業に必要な資格の取得方法や学習過程について解説します。
保健師になるためのルート
保健師になるには、「看護師免許」と「保健師免許」の2つの国家資格が必要です。そのため看護師と保健師、両方の国家試験への合格を目指さなければなりません。
これまでは、看護師養成学校を卒業して看護師免許を取得し、のちに保健師養成学校に通うのが一般的でした。しかし、近年では看護師と保健師の国家試験を同時に受験できる4年制大学や専門学校も増えてきました。
また国の省庁や都道府県の保健所、市区町村の保健センターで保健師として働くためには、国家公務員試験や地方公務員試験にも合格する必要があります。
助産師になるためのルート
助産師として働くためには、「看護師資格」と「助産師資格」の2つの国家資格が必要です。そのためには、大学・短大・専門学校・養成所を卒業した後、国家資格試験に合格する必要があります。
4年制大学の看護学部や看護学科には「助産師養成課程」が設けられています。卒業見込みの年に2つの国家試験を受験して合格すれば、卒業後すぐに助産師としてキャリアのスタートが可能です。
しかし、4年間で看護師と助産師両方の学習をしなければならないため、効率的ではあるものの簡単な道のりではありません。他にも、4年制大学や3年制の短大・専門学校で看護師資格を取得した後に、1年制の助産師養成所に通うルートもあります。
看護師になるためのルート
看護師になるためには、国家資格である「看護師資格」を取得する必要があります。看護師資格を取得するためには、文部科学大臣指定の学校または厚生労働大臣指定の看護師養成所を卒業し、看護師国家試験に合格しなければなりません。
学校の種類には、4年制大学、3年制の短大・専門学校があります。4年制大学や3年制の短大・専門学校の看護師養成課程を卒業すると、看護師国家試験の受験資格が得られます。その後、看護師国家試験に合格して働き始めると、「看護師」としてのキャリアの開始です。
准看護師になるためのルート
准看護師として働くには、各都道府県で実施される試験に合格して准看護師免許を取得する必要があります。
受験するためには、下記の要件を満たす必要があります。
- 准看護師養成所を卒業(最短2年)
- 高校の衛生看護科を卒業(最短3年)
准看護師養成所には、全日制と定時制があります。全日制の養成所では週3日、定時制の養成所では週5日授業をおこなうケースが多く、働きながらの資格取得も目指せます。
保健師・助産師・看護師資格の欠格事由

欠格事由とは、資格試験に合格しても免許が与えられない理由を指します。第9条では、免許が与えられない具体的な理由が定められています。詳細は以下のとおりです。
【第9条】
- 罰金以上の刑に処せられた者
法律に基づいて罰金以上の刑罰を受けた場合、その人には免許が与えられないことを意味します。 - 業務に関する犯罪や不正行為をした者
罰金以上の刑に該当しない場合でも、保健師・助産師・看護師・または准看護師の業務に関連する犯罪や不正行為があった場合も免許が与えられません。 - 心身の障害
厚生労働省令で定められる基準により、心身の障害が原因で業務を適正におこなえないと判断される者にも免許が与えられない場合があります。 - 麻薬、大麻、あへんの中毒者
麻薬や大麻、あへんの中毒者も免許を取得できません。
第14条では保健師・助産師・看護師が第9条に該当する事由に至った場合や、品位を損するような行為をした場合に、厚生労働大臣による下記の処分が定められています。
- 戒告
軽度の違反行為には戒告が与えられる場合があります。 - 3年以内の業務停止
より重い違反の場合、3年以内の業務停止処分が科される場合があります。 - 免許の取消し
もっとも重大な処分として、免許の取消しがおこなわれる場合があります。
欠格事由や処分についての理解は、保健師・助産師・看護師としての職業倫理を守るうえでも大切です。
保健師助産師看護師法の名称独占・業務独占に関する規定

保健師助産師看護師法の第29条から第32条には、名称独占および業務独占に関する規定が含まれています。第29条から第32条には、特定の職業に従事する者だけが特定の業務をおこなえる旨が定められています。
名称独占と業務独占の違い
名称独占と業務独占は、医療職に関連する資格を取得する際において押さえておきたい概念です。まず、名称独占に該当する資格は、国家試験の他、都道府県や法律で指定された団体がおこなう試験で取得されます。
名称独占資格は、資格を所有する人だけが、その名称を名乗ることが許されています。名称独占資格に該当する名称を使って特定の業務をおこなうと、法律上の罰則が適用されるので注意してください。
たとえば、理学療法士の業務の一つであるリハビリは、理学療法士の資格を持たない者でもおこなえます。しかし、無資格者が「理学療法士」と名乗ってリハビリをおこなうのは法律違反となり、処罰の対象です。
業務独占資格とは、資格を持つ人だけがその業務を独占的におこなえる資格です。無資格者がその業務をおこなうと、たとえ特定の名称を名乗っていなくても法律違反となり、罰則が適用されます。
名称独占と業務独占は異なる意味を持つため、それぞれの資格の特性を理解することが大切です。
名称独占資格|保健師
保健師は名称独占資格に該当しますが、業務独占資格には該当しません。つまり、資格を持たない人が保健師としての業務をおこなっても、法律上の処罰にはつながりません。保健師の主な業務が健康相談や生活指導であり、命や財産に直接的な危害を及ぼす可能性が低いためです。
しかし、無資格者が保健師と名乗って業務をおこなうと、処罰の対象になります。保健師の資格は専門的な知識を持っている証明であり、社会的な信用を保証するためです。資格を持つ保健師が業務をおこなうからこそ、適切な相談や指導がおこなえるため、資格の重要性が際立ちます。
業務独占資格|助産師・看護師・准看護師
助産師・看護師・准看護師は業務独占資格に該当するため、資格を持たない人は助産師や看護師、准看護師としての業務をおこなえません。助産師・看護師・准看護師としての資格の取得は、患者の安全を守り、医療サービスの質を確保するうえで非常に重要といえるからです。
資格を持たない者が該当する業務をおこなった場合は、法律違反として処罰されます。保健師助産師看護師法を理解し各資格の特性を把握することは、医療従事者としての責任を果たし、よりよいサービスを提供するためにも欠かせません。
保健師助産師看護師法における守秘義務と罰則

保健師助産師看護師法の第42条の2において、「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」と明記されています。医療従事者が患者や利用者の個人情報を守る責任を示しており、患者の信頼を維持するための基本的なルールです。
さらに守秘義務は、保健師や看護師、准看護師の資格を失った後でも継続して適用されます。業務を終えた後も患者のプライバシーを尊重し、情報漏洩を防ぐための措置です。具体的な罰則については、業務停止や刑事罰などがあります。守秘義務の違反は、患者の信頼を損ねるだけでなく、医療機関全体の信用をも危うくするため、厳格な遵守が求められているのです。
まとめ|保健師として働くなら保健師助産師看護師法を把握しておこう
本記事では、保健師助産師看護師法の主要な内容について、条文を踏まえながら具体的な内容を解説しました。名称独占・業務独占・守秘義務などの規定は、医療従事者としての責任や職務の範囲を明確にし、患者の安全と信頼を守るための重要なポイントです。
法律を正しく理解し、日常業務に生かせれば、よりよい医療サービスの提供につなげられるでしょう。今後、保健師や看護師としてのキャリアを築くためには、法律に基づいた知識を深めていくことが大切です。
保健師専門の転職サポート!32年の実績!
転職サポートに登録(無料)【新着】お役立ちブログ
- 2025年11月17日 産業保健師は未経験からでも始められる!キャリアチェンジ完全ガイド
- 2025年11月17日 【2025年最新版】保健師・看護師の平均年収を徹底解説|年代・地域別の違いと収入アップ術
- 2025年11月17日 保健師はフルリモート勤務できる?求人の実情と応募条件・働き方を解説
- 2025年10月20日 産業保健師の転職はエージェント活用で差がつく!未経験でも安心の理由と賢い使い方
- 2025年08月28日 【30代で産業保健師に】未経験からでも目指せる?転職を成功に導く準備とポイント