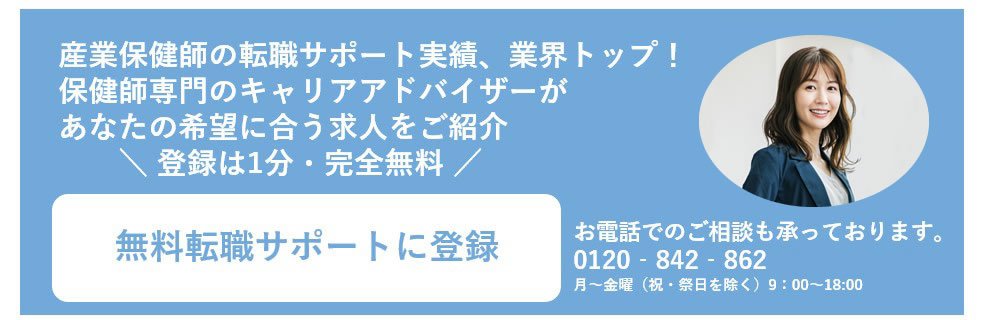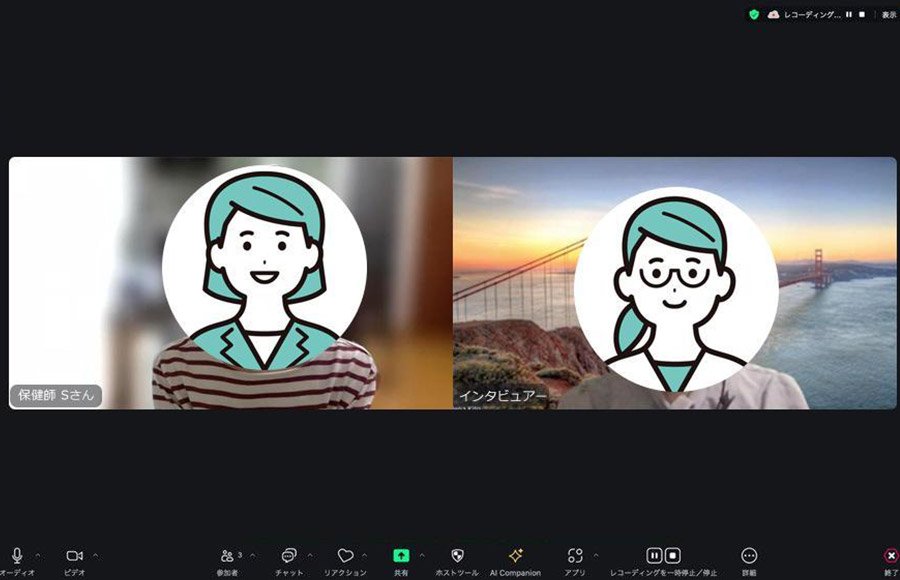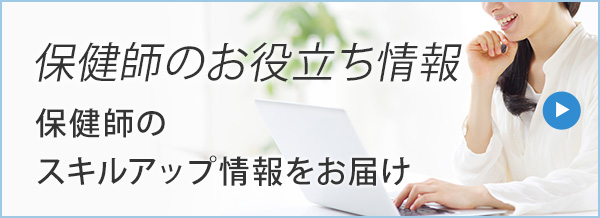【保健師】仕事内容・役割保健師に向いている人の特徴とは?向き不向きや職場別の適性・やりがい
公開日:2023年08月04日
更新日:2025年06月26日

こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。
「自分は本当に保健師に向いているか、不安になる...」
「保健師として活躍したいけど、『自分には向いていないかも...』と想いが頭をよぎる」
「もし向いていないと感じたら、どうすればいいのか知りたい」
このような悩みを持つ人のために、アポプラス保健師のライターチームが疑問を解決する記事を執筆しました。
行政機関や一般企業・学校・病院などで、病気の予防に携わり、健康維持・増進を図るための重要な役割を保健師は担っています。
本記事では、保健師に向いている人・向いていない人の特徴、保健師の種類とやりがい、保健師に向いていないと感じたときに行う対処法などを解説します。また、現場保健師のリアルな声も紹介しているため、現役保健師や保健師を目指している人にも役立つ内容です。
最後までお読みいただくことで、「自分にぴったりの産業保健師像」が明確になり、理想のキャリアプランを描きながら、安心して次の一歩を踏み出せるようになります。「保健師が向いていないかも」と感じている方も、自身の強みや向いている人の特徴、現場保健師のリアルな声を知ることで保健師の適性があることを実感できるかもしれません。
ぜひ、ご自身の理想像を思い描きながら読み進めてください。
目次
- ・保健師に向いている人の5つの特徴
- ・【診断チェックリスト】あなたは保健師に向いている?
- ・保健師の種類とやりがい
- ・保健師に向いていない人の3つの特徴
- ・保健師に向いていないと感じたときの対処法
- ・現場保健師のリアルな声
- ・まとめ|保健師の向き・不向きよりも大切なこと
保健師に向いている人の5つの特徴

保健師は、さまざまな人と関わる職業です。そのためコミュニケーション力をはじめ、粘り強さ・柔軟性・安心感・学び続ける姿勢などの特性を持った人に向いています。
ここでは、保健師に向いている人の5つの特徴について、それぞれ解説します。
1. コミュニケーション力が高く、相手の話に耳を傾けられる
保健師はさまざまな人と関わる仕事のため、幅広い人と円滑にコミュニケーションを取れる人に向いています。健康相談や保健指導の際には、相手の話を傾聴し、悩みや不安を丁寧に引き出す「聴く力」が必要です。
そのうえで、一方的に指導するのではなく、相手に寄り添いながらわかりやすく提案する姿勢が大切です。
保健師の業務には、研修会を開催したり、チームで連携したりする場面もあります。その際には、幅広い年齢や性別の人を相手にしたり、チームで協力したりする力が求められます。
たとえば、ある企業で保健師が担当したストレスマネジメント研修では、初回の資料の内容が専門的すぎたり、若手社員とベテラン社員に響くポイントが違ったりして、思ったほどの反応が得られませんでした。2回目には、参加者の属性に応じて話す順番や例え話を工夫したり、実際に使えるセルフケアをその場で体験できるワークに取り入れたりすることで、反応が大きく変化しました。参加者からは「わかりやすかった」「実践できそう」などと感想をいただき、研修の満足度が大きく向上しました。
また、別の場面では、休職者の職場復帰支援の際に、産業医・人事・上司と密に連携しながら、休職者の体調や不安に寄り添った調整が求められました。面談では、「本当に戻れるのか不安」という本人の声に耳を傾けつつ、復職後の業務内容やペースについて各所と調整を行い、最終的に無理のない形での職場復帰を実現できました。
このように保健師の現場では年齢や性別、職種の垣根を超えて、多様な人と信頼関係を築き、状況に応じて伝え方や関わり方を柔軟に変えていく力が求められます。
2. 地道な努力を続けられる粘り強さがある
地道な努力を続けられる粘り強さがある人に、保健師は向いています。保健師は、主に病気の予防に携わり、健康維持・増進に寄与します。
病気や怪我の治療と比べて、結果がすぐに表れないことが少なくないでしょう。そのため、やりがいを感じにくいときもあるかもしれませんが、それでも根気強く取り組むことが重要です。
モチベーションを保ち、自分の役割に自信を持って地道な努力を続けられる人が、保健師として長く活躍できる素質をもっています。
以下に、実際の保健師の仕事に即したケースを紹介します。
・事例①半年かけて信頼を築いた禁煙支援
ある企業で働く産業保健師は、喫煙習慣がやめられない40代男性の支援にあたりました。最初の面談では、「関係ない」と反発されましたが、それでも毎月小さな声かけや体調に触れる話題から関係づくりを続けました。半年後本人のほうから「外来を受けてみようかな」と話し始めたそうです。
結果が出るまでに時間がかかるものですが、「信頼関係はすぐには作れない」と産業保健師自身が心得ていたからこそ、粘り強く続けることができたといいます。
・事例②1年かけて生活習慣を改善
保健センター勤務のある保健師は高血圧に悩む中高年の男性に対して、毎月の面談で生活記録を一緒に見直す支援を1年間継続しました。すぐには数字に変化は見えませんでしたが、徐々に生活リズムが安定し、薬の量も減らすことができたそうです。
成果が見えるまでには時間がかかりましたが、1回1回を丁寧に行うことで、成果につなげたケースといえます。
このように、「すぐに結果が出なくても、目の前の人の変化を信じて向き合い続けられる人」は、保健師にとても向いていると言えます。
粘り強さと真摯な姿勢こそが、現場で信頼される保健師としての土台を築いていくのです。
3. 柔軟性・臨機応変な対応力がある
保健師には、柔軟性や臨機応変な対応力も大切です。相談をしてくる人は、一人ひとり状況や背景が異なります。そのため、すべてマニュアル通りに対応するのではなく、それぞれに合わせた柔軟な支援が求められます。
また、社内や地域の人と連携して活動するとき、方針や制度が変更されたときなどには柔軟かつ臨機応変に対応していく力が必要です。
事例①生活習慣指導から「育児と仕事の両立」支援へとシフト
ある産業保健師は、生活習慣の乱れによる体調不良を訴える20代女性社員の面談を担当しました。最初は睡眠や食事の指導を行っていましたが、話を深堀りするうちに育児と仕事の両立に悩んでいることが主な原因とわかり、指導方針を変更。「時短勤務制度」や「社内の育児支援制度」の紹介を行い、育児と仕事のバランスに焦点を当てた支援に切り替えました。
一見健康相談に見えても、その背景にある課題に気づき、支援内容を柔軟に変更できる対応力が活かされたケースです。
状況に応じて支援の方向性を見直したり、環境の変化に素早く対応したりできる力は保健師としての信頼や満足度を高めるうえでも非常に重要だといえます。
4. 他者に安心感を与える雰囲気・信頼感がある
保健師は「安心感」や「信頼感」を与えられる人柄の人に向いています。相談を受ける立場として、相手の悩みや不安を引き出し、適切なアドバイスをするためには「話しかけやすさ」や「安心感」が欠かせません。相手がリラックスして話せる雰囲気を作り、本音を引き出すことが大切です。
相手の状況や要望を理解し、一人ひとりに合わせた支援をするためには、信頼構築力が必要不可欠です。この信頼構築力も、保健師としての大切な適性の一つといえるでしょう。
5. 変化を前向きにとらえ、学び続ける姿勢がある
保健師には、変化を前向きにとらえ、学び続ける姿勢が大切です。公衆衛生や予防医学の分野は日々進歩し、知識や技術も次々とアップデートされています。
また、社会や制度も時代に合わせて変化し続けるでしょう。変化に合わせて、常に知識をアップデートしていける人が、保健師として長く活躍できます。勉強熱心さや、成長意欲も保健師としての適性の一つといえます。
【診断チェックリスト】あなたは保健師に向いている?

「保健師って自分に向いているのかな?」そのようなモヤモヤを感じているあなたへ。
下の10項目、あなたはいくつ当てはまりますか?
簡単なセルフチェックで、保健師の適性が自分にあるかを確認してみましょう。
【保健師適性チェックリスト】
| No. | 質問内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 人の話を聞くのが好きだと感じる | □ |
| 2 | 相手の立場や気持ちに立って考えることが自然にできる | □ |
| 3 | 1対1の関係づくりが得意である | □ |
| 4 | 相手の「困りごと」を引き出し、整理するのが好きだ | □ |
| 5 | チームや地域など"集団"全体を見ることが得意だ | □ |
| 6 | 一方的な指示よりも「サポートする」役割にやりがいを感じる | □ |
| 7 | 地道な記録・報告などもきちんとこなすのが得意である | □ |
| 8 | 体調・生活リズムなど、ヘルスケアへの関心が高い | □ |
| 9 | 状況に合わせて柔軟に対応することが得意だ | □ |
| 10 | 知識をアップデートしていくことが苦ではない | □ |
上記の質問内容のうち、「はい」と答えられた項目が多いほど、保健師の適性があるといえます。あくまでも簡易的なセルフチェックではありますが、一つの参考にしてみてください。
保健師の種類とやりがい

保健師に向いている人は、健康増進や病気の予防につながる活動ができる点、幅広いスキルが得られる点にやりがいを感じます。ここでは、保健師の種類とやりがいについて、それぞれ紹介します。
行政保健師
行政保健師とは、行政機関で働く保健師のことです。
具体的には、次のような場所に公務員として勤務しています。
- 保健センター
- 保健所
- 地域包括支援センター
新生児から高齢者まで、幅広い地域住民の健康増進や疾病予防に携わっているのです。
勤務先によって異なりますが、次のような業務を担当しています。
- 健康相談、保健指導
- 母子保健活動
- 介護予防活動
- 健康教室
- 健康課題の調査、保健計画や施策の立案と運営
こういった地域に密着した活動を通して、地域全体の健康を守ることは、大きなやりがいにつながります。
産業保健師
産業保健師とは、一般企業で働く保健師です。従業員が心と体の健康を維持しながら、安全に働けるよう支援する役割を担っています。
製造業、医療・福祉、運輸業などさまざまな業界の企業に所属し、以下のような業務を担当しています。
- 健康診断の実施や診断結果を基にした助言
- ストレスチェックやメンタルヘルスケア
- 健康に関する研修会の開催
- 職場環境の改善
産業保健師は保健活動を通して、従業員が健康に関心を持ち生活習慣を改善し、病気の予防につながったときにやりがいを感じることができるでしょう。
また、産業保健師が担当する業務には次のような広範な知識やスキルが必要とされます。
- 医療、メンタルヘルス、労働安全衛生法に関する知識
- カウンセリングスキル、コーチングスキル
- コンサルティング力
経験を積むことで習得できる幅広いスキルは、将来他の分野でも活かせるはずです。成長意欲の高い人にとって、業務を通してさまざまなスキルを身につけられる点は大きな魅力といえます。
学校保健師
学校保健師とは、学校で勤務する保健師のことです。
生徒や教職員に対して、心身の健康維持に関する次のような業務を担当しています。
- 生徒や教職員の健康管理
- 怪我や病気の応急処置
- メンタルヘルスケア
- 衛生環境管理、感染症対策
相手に寄り添い、年齢や状況に合わせられるコミュニケーション能力が求められます。繊細な時期の生徒に寄り添い、心身の健康をサポートしながら成長を見守れることは、大きなやりがいとなるでしょう。
病院保健師
病院保健師は、病院やクリニック、健診センターなどで働く保健師のことです。
業務内容は勤務先によって異なりますが、次のような業務を担当しています。
- 入退院の調整、医療機関や福祉施設などとの連携
- 感染症対策室の運営
- 健康診断の補助
- 保健指導
- 予防接種の補助
医師や看護師などと連携を取りながら、チームで活動する力が求められます。職員に対する健康維持・増進に関わることが、より多くの患者の健康支援につながる点にやりがいを感じるでしょう。
また、医療分野の情報に触れる機会が多いため、常に新しい知識を学習できます。さらに、採血の補助も行うため、医療に関する技術も学べます。このような知識や技術を習得できることは、幅広いスキルを身に付けたい人にとって魅力といえるでしょう。
保健師が人気の職種である理由や、保健師として働く人々が、具体的にこの仕事のどのような点に魅力ややりがいを感じているのか、実際の保健師の体験談とともにご紹介します。
「保健師」は、「医師」「看護師」などに比べると耳にすることの少ない職業です。ここでは、保健師が具体的にどのような職業で、資格取得後はどういった仕事に就けるのかについてご紹介します。
保健師に向いていない人の3つの特徴

保健師は、病気予防や健康増進を目的にさまざまな人と関わる職業のため、専門的な知識・スキルに加えて求められる適性があります。適性がないと、円滑に業務を進められない・ストレスを感じる・やりがいを感じられないなどの理由で、保健師として働き続けられないかもしれません。
ここでは、保健師に向いていない人の3つの特徴を解説します。
1. 一人で黙々と作業したいタイプ
1人で黙々と作業をしたいタイプの人は、保健師に向かないかもしれません。保健師は、人と関わる時間が非常に多い職業です。
健康相談や保健指導では、多様な人と信頼関係を築いて悩みやニーズを引き出し、一人ひとりに合わせたわかりやすいアドバイスが求められます。また、研修会を開いたり、他の職種と連携を取りながらチームで活動したりする場面もあります。
人とコミュニケーションを取ることにストレスを感じる人は、業務を円滑に進められない可能性があり、保健師を長く続けるのは難しいでしょう。
2. 成果や評価がすぐ欲しいタイプ
成果や評価がすぐに欲しい人は、保健師に向いていない可能性があります。保健師が携わる病気の予防や、健康増進に関する活動の成果は、すぐに見えないことが多いためです。
結果が数値に表れにくいため、評価されにくいことも少なくありません。そのような状況でも、保健師の仕事に自信を持って、地道な努力を続けることが大切です。
そのため、成果や評価がすぐに欲しい人は、やりがいや達成感が感じられずに、モチベーションを保ちにくいでしょう。
3. 想定外の事態に不安を感じやすい人
想定外の事態に不安を感じやすい人も、保健師には向かない可能性があります。保健師の業務は、予定外の相談や、予測できない課題に対応することが珍しくありません。
そのため、柔軟かつ臨機応変に対応していく力が求められます。想定外の事態に不安を感じやすい人は、ストレスが溜まりやすく、保健師の仕事に適応しにくいでしょう。
保健師に向いていないと感じたときの対処法
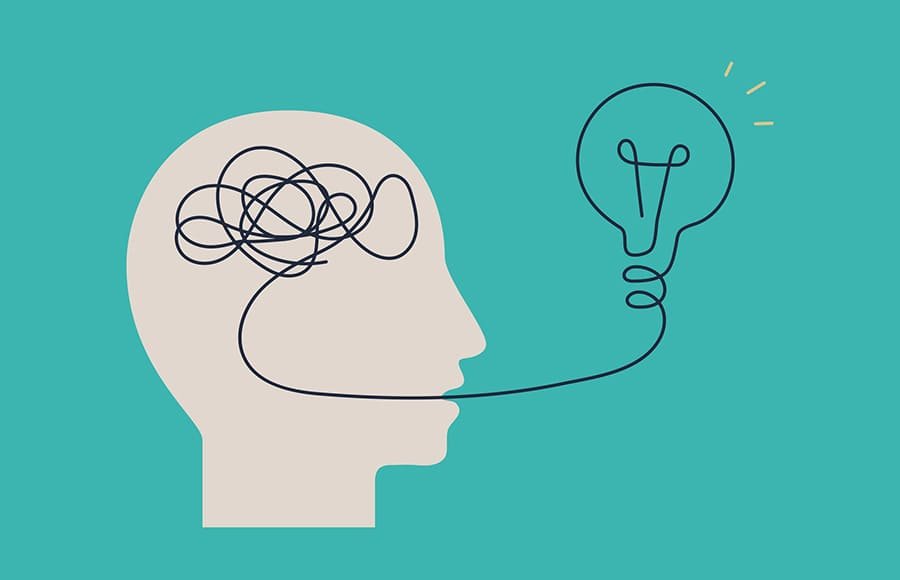
ときには保健師に向いていないと感じることがあるかもしれません。しかし、自分に保健師が向いていないと感じた場合でも、すぐに辞めるべきとは限りません。
まずは、なぜ自分に保健師が「向いていない」と感じたのか、その理由を整理してみましょう。そのうえで、弱みを補うためのスキルアップや、支援体制の活用を考えることが大切です。
たとえば、コミュニケーションに不安を感じたら、コーチングスキルを学べる研修に参加してみるのも一つの方法です。また、業務量の多さや残業が続くことに負担を感じている場合は、上司に業務量の調整を相談してみるとよいでしょう。
さらに、職場を変えることで、悩みが解消する場合もあります。保健師には、行政機関や一般企業など、さまざまな就職先があるため、業務内容や求められる資質はそれぞれ異なります。
そのため、保健師に向いていないと感じていても、実際には今の職場が合っていないだけの可能性もあるのです。働く職場を変えることで、自信を持って活躍できるようになるケースもあります。
現場保健師のリアルな声

ここでは、現場保健師2名のリアルな声を紹介します。
産業保健師 Sさんの体験談
Sさんは、約4年間、急性期病院で看護師として働くなかで、生活習慣の積み重ねが原因で重い病気を発症する患者さんを何人も見てきたSさん。治療の手助けはできても、「未然に防ぐ支援」はできていないもどかしさを感じていました。そんなときに保健師に興味を持ち、1年間学校に通い、保健師の資格を取得しました。卒業後は行政保健師として、市町村で乳幼児健診や特定保健指導、精神疾患のある方の支援など、幅広い業務を経験しています。一方で対象者との関わりが一過性になることも多く、支援の継続性に課題を感じていたといいます。「一人ひとりのペースに合わせて、ゆっくり伴走できる仕事がしたい」という思いが強まり、次に選んだのが「産業保健師」でした。
産業保健師として働き始めてからは、健康診断後の面談、メンタル不調の早期発見と支援、復職支援、日常的な健康相談など、より"その人の生活"に踏み込んだ支援ができるようになったとSさんはいいます。
たとえば、こんな場面がありました。
健診後の面談で、血圧が高い40代の男性社員に生活改善を促すよう話をしました。最初は少し壁がある様子でしたが、何度か面談を重ねるうちに、仕事終わりの飲酒が習慣になっていること、家族との時間が取れずストレスを感じていることなど、少しずつ本音を話してくれるようになりました。小さな変化に伴走しながら支援できることに、保健師としてのやりがいを感じた瞬間でした。
こうした日々のやりとりから、「支援が相手の行動を変え、生活を変える」実感を得られるようになったと話します。
Sさんは現在の職場に、アポプラス保健師を通じて「紹介予定派遣」で就職しました。実際に働きながら職場の雰囲気や業務内容を見極められる点に、安心感があったといいます。
就職前に企業について理解できた点や、アポプラス保健師のコーディネーターとの丁寧な面談により、疑問や悩みを解消できた点がよかったとSさんは感じています。Sさんは、今後は「相談しやすい専門職」として働く人の身近な存在でいることを目指しているそうです。
産業保健師として活躍をしているSさんのリアルな声をより知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。
本記事では、看護師として臨床現場で働いた後、保健師資格を取得して行政保健師、産業保健師としてキャリアを積んだ現役の産業保健師さんにお話を伺いました。転職をする中で感じた理想とする働き方や実際に取り組んだことに加え、転職を成功させる重要なポイントについても解説をしていきます。
産業保健師Aさんの体験談
Aさんは、病院勤務を経験後に保健師免許を取得しました。その後、行政保健師を経て、産業保健師として7年間企業に勤務。そこで働き方に迷いを感じ、異なる分野から現在の課題に挑むために、働きながら通える大学院に進学しました。
大学院で学ぶなかで様々な分野への興味が強くなり、学びを深める中で、「もっと多様な働き方をしている企業や、その現場を知りたい」という気持ちが芽生え、アポプラス保健師に登録したそうです。面談では、これまでのキャリアだけでなく、大学院での学びや、今後挑戦したいテーマについても丁寧にヒアリングしてくれたといいます。そこで現在勤める企業を紹介され、健康推進室の立ちあげに参画することになりました。制度や仕組みがないところから始めるのは、大変な反面、大きなやりがいがあったとAさんはいいます。
特に意識したのは、「誰もが相談しやすい窓口づくり」です。支援対象を"全従業員"とし、多様性を尊重する体制づくりに注力してきたAさん。まさに、大学院での学びを実践の場で活かしているといえます。
今後は、従業員一人ひとりが自分らしく働けるよう、健康面の支援をしていきたいとAさんは語ります。アポプラス保健師は、正社員として雇用されたあとでも相談できる環境が整っているため、現場で一人になりがちな産業保健師にとって心強い存在となっているそうです。
産業保健師のAさんが転職した経緯や実際の活動内容をさらに詳しく知りたい方は、下記の記事を読んでみてください。
本記事では産業保健師インタビューをご紹介します。
まとめ|保健師の向き・不向きよりも大切なこと
保健師に向いている人は、努力を続けられる粘り強さ・柔軟性・安心感や信頼感を与えられる人柄・学び続ける姿勢などの特徴を持っている人です。一方、向いていないのは、人との関わりが苦手な人や成果がすぐ欲しい人、想定外の事態に不安を感じやすい人などです。
ただし、保健師に向いていないと感じても、すぐに辞めるべきとは限りません。なぜ「向いていない」と感じたのか理由を整理し、弱みを補うためのスキルアップや、支援体制の活用を考えることが大切です。
また、保健師には行政機関や一般企業などさまざまな就職先がありますが、業務内容や求められる資質はそれぞれで異なります。保健師に向いていないと感じていても、実際には今の職場が合っていないだけの可能性もあるのです。
保健師として働くうえで大切なのは、単純な向き・不向きだけではなく、自分が持っているスキルや性格に合った、長く働き続けられる環境を見極めることです。どのような環境が自分に合っているのかわからないと感じている方は、一人ひとりの悩みに真剣に向き合うアポプラス保健師にぜひ相談してみてください。
保健師専門の転職サポート!32年の実績!
転職サポートに登録(無料)【新着】お役立ちブログ
- 2025年11月17日 産業保健師は未経験からでも始められる!キャリアチェンジ完全ガイド
- 2025年11月17日 【2025年最新版】保健師・看護師の平均年収を徹底解説|年代・地域別の違いと収入アップ術
- 2025年11月17日 保健師はフルリモート勤務できる?求人の実情と応募条件・働き方を解説
- 2025年10月20日 産業保健師の転職はエージェント活用で差がつく!未経験でも安心の理由と賢い使い方
- 2025年08月28日 【30代で産業保健師に】未経験からでも目指せる?転職を成功に導く準備とポイント