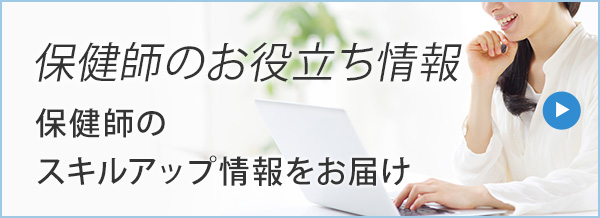【保健師】業界情報産業保健師の現場で求められるメンタルヘルス対策とは
公開日:2015年08月25日
更新日:2025年06月25日

こんにちは、保健師転職のアポプラス保健師ライターチームです。
「メンタルヘルス対策に携わってみたいけど具体的に何をするのかわからない!」
「産業保健師としてメンタルヘルス支援の専門性を高めるにはどうしたらいい?」
「職場のメンタルヘルス対策を強化するためのスキルを把握したい。」
このような悩みを持つ人のために、アポプラス保健師のライターチームが疑問を解決する記事を執筆しました。
企業におけるメンタルヘルス対策は、年々重要度が増してきています。メンタルヘルスのために産業保健師が果たすべき役割も、大きくなってきているといえるでしょう。
産業保健師が実施できる取り組みはさまざまです。なぜ、メンタルヘルス対策が今まで以上に求められているのか、具体的にはどのような対策があるのかなどについて紹介します。
この記事を読むことで、ストレスチェックの実施方法からハラスメント対策の事例まで、明日から現場で実践できるメンタルヘルス対策の具体的な手法が身につきます。また、産業保健師としての専門性を高めるために必要な資格やスキルが明確になり、今後の成長に役立つ実践的な知識を得ることもできるでしょう。
目次
- ・企業におけるメンタルヘルスの重要性
- ・産業保健師が関わるメンタルヘルス対策
- ・産業保健師のメンタルヘルス対策を強化するために必要なスキル
- ・産業保健師としてよりよい職場で働くには?
- ・まとめ|メンタルヘルス対策は産業保健師の重要な役割の一つ
企業におけるメンタルヘルスの重要性

近年、さまざまな企業においてメンタルヘルスの重要性が注目されています。企業が健全かつ順調に業績を伸ばしていくためには、従業員一人ひとりの心身の状態が非常に大切なのです。
メンタルヘルス不調の従業員にできるだけ早く気づき、対策を取ることで、企業は優秀な人材の流出を防げるでしょう。各従業員が、身体だけでなくメンタルも健康であれば、より高いパフォーマンスを期待できます。そして、それぞれが高いパフォーマンスを維持できることで企業としての業績も伸ばせるのです。
しかし、ひとたびメンタルヘルスに不調をきたしてしまうと、生産性の低下や休職・離職にもつながってしまいます。それだけではありません。労災請求や損害賠償責任といった問題にも発展し、場合によっては企業イメージまで落としてしまう恐れがありますので、従業員の心身の健康・安全に対する配慮は何よりも重要です。
働き方の多様化に伴うメンタルヘルスの課題
メンタルヘルスへの対策が重要視されるようになった背景には、働き方の多様化が影響していると考えられます。人手不足による長時間労働の問題や、コロナ禍以降のテレワークの普及など、労働環境の変化によりメンタルヘルスに不調をきたしてしまう従業員が増えたのです。
社会情勢の変化とともに、ある程度の労働環境の変化は避けられないかもしれません。そうした社会の中でも、メンタルヘルスに関する課題に常に向き合い解決に向けて動くことが、今後大切になるでしょう。日々の小さなストレスを、無視しないことも重要です。
企業における産業保健師の役割の変化
労働環境の変化とともに、企業における産業保健師の役割も少しずつ変化しています。以前は健康診断の結果を確認し、生活習慣病を防ぐための対策を促すことが重要でした。
しかし、最近は生活習慣病だけでなくメンタルヘルス不調も増えているため、総合的に取り組むことが必要になっています。
企業は、メンタルヘルスケアにもきちんと向き合わなくてはいけません。そのような流れの中で、産業医よりも近い立場にいる産業保健師は、さまざまな悩みのよき相談相手としてこれまでとは違った役割も担っていくようになるでしょう。産業保健師の存在は、ますます大切になると考えられているのです。
産業保健師が関わるメンタルヘルス対策

企業で働く従業員のメンタルヘルスを守るためには、職場内でのメンタルヘルス対策が重要です。深刻化する前になんらかの対策を施すことで、改善へと導きやすくなるでしょう。
そのためには従業員と産業保健師の向き合い方が大切で、さまざまな方法が考えられます。たとえば、ストレスチェックを実施したり、ハラスメントを防止する対策を取ったりといったことがあります。他にも、労働環境の改善や相談窓口の設置、メンタルヘルス不調により休職した従業員に対するフォローアップなどを、状況に応じて行ってみてください。
従業員が心身ともに健康で常に前向きな気持ちで仕事に取り組めるよう、産業保健師としてできるメンタルヘルス対策について詳しく説明します。
ストレスチェックの実施とフォローアップ
メンタルヘルスの不調を早期に知るためには、ストレスチェックが有効です。ストレスを受けている状態だと自他ともに気付き、それ以上の悪化を未然に予防できれば、従業員にとっても企業にとってもメリットが大きいでしょう。
2015年、企業で働く従業員のストレス状況を確認し改善するための「ストレスチェック制度」が施行されました。従業員50人以上の事業場では、年に1回のストレスチェック実施が義務付けられたのです。実施状況については、労働基準監督署へ報告もしなくてはいけません。
より具体的にイメージできるように、実際の現場でストレスチェックの実施とフォローアップでうまくいった事例を、下記でみていきましょう。
【ストレスチェック・フォローアップの事】
ある社会福祉法人において、ストレスチェックの分析結果から、特定部署に高ストレス者が集中していることが判明しました。
コミュニケーションがうまくとれていないことが一つの原因として考えられたため、あいさつ運動を推進。その結果、前年度と比べて高ストレス者が半減するなどメンタルヘルスの状況が大きく改善した。
ストレスチェックの実施を従業員のメンタルヘルス不調の改善につなげるためには、上記事例のように分析結果を活かしたフォローアップの仕組みが重要です。ストレスチェック制度を上手に機能させていくためにも、まず「いつ」「誰が」「どのように」実施するのかなどをきちんと話し合い、明文化していくようにしましょう。
そして、従業員にストレスチェック制度の内容を丁寧に伝え、そのうえで質問票を配っていきます。チェックは、オンラインで実施しても問題ありません。
チェック後の結果は、産業保健師や産業医などから直接従業員本人へ通知されます。強いストレスを受けていると評価された従業員に対しては、適宜面接をするなど状況に応じたフォローアップも行います。
注意が必要なのは、質問票を回収する際などに企業の人事担当者が関わってはいけない点です。人事担当者らが質問票に書かれた内容を見ることは禁止されています。ストレスチェックの結果は、企業ではなく産業保健師や産業医などが責任を持って保管しなくてはいけません。
チェックを実施する側と従業員との信頼関係が大切になるため、管理を徹底させましょう。
ハラスメント防止と労働環境の改善
セクハラやパワハラなど、企業内でのハラスメントはメンタルヘルス不調の大きな原因です。ハラスメントを受けている側は深く傷つき悩んでいても、ハラスメントを行っている側は自分の行為に気付いていないといったケースもあるでしょう。
そのような労働環境を早期に改善させ、仕事をするうえで健康的で快適な環境を維持できるような施策を取ります。具体的な施策の事例を確認していきましょう。
【ハラスメント防止・労働環境改善の事例】
ある大規模外食産業では、本部の管理職・部門長向けに研修を実施していましたが、近年は現場の店長向けの専用研修も導入しました。
人事部内の専用窓口に加え、心身の健康相談窓口や労働組合による店舗巡回時のヒアリングなど、複数の相談ルートを確保して従業員が相談しやすい環境を整えています。
上記の事例のようにハラスメントをしている側にも気付きを与え、受けている側が声を上げやすい環境を作るためには、一つの相談ルートだけにこだわりすぎないことが重要です。悩みをじっくりと聞き、早期にハラスメントを発見して対応するなど、メンタルヘルスの原因を取り除く対策を進めてください。
従業員の相談窓口の運営
悩みを抱えてストレスを感じている従業員がいつでも気軽に相談できる窓口を、企業内に用意しておくことも大切です。問題が大きくなりすぎてしまう前に話せる場所があれば、うつや休職といった状況を未然に防げる可能性も高いでしょう。
もちろん、相談窓口を設置し運営するだけでなく、日頃から従業員との信頼関係を築いておくことも重要です。信頼関係が構築されていない状態では、悩みがあっても相談したいと思ってもらえません。
従業員の状況に寄り添って、相談しやすい環境を作った事例として、下記のケースを紹介します。
【従業員の相談しやすい環境づくりの事例】
ある大規模病院では、産業医・保健師といった専属の産業保健スタッフによる、メンタルヘルス相談窓口を設置しました。窓口には院内の臨床心理士も加え、男女両方の担当者を複数配置することで、相談者が話しやすい相手を選べる体制を整えています。
また相談窓口の存在を院内に周知するとともに、産業医が積極的に現場に出向いて日常的なコミュニケーションを図り、職員が相談しやすい関係性を構築しています。
上記の事例のように、まずは従業員の立場になって、どのようにしたら相談しやすくなるかを徹底的に考えることが重要です。そのうえで、何か問題が起きてしまったときだけでなく何も問題のない時期から、従業員とよりよい関係を築いていけるよう心がけておきましょう。
休職者の職場復帰支援
メンタルヘルス不調で休職していた従業員は、復帰するまでに高いハードルを感じることが多く、そのような休職者が無事に職場へ復帰するには、産業保健師の果たす役割が大切です。復帰後にも必要に応じたフォローアップを続けることで、再発を防ぎやすくなります。
産業医や上司などとも連携し、休職中も定期的に連絡を取るようにしましょう。現状を確認し悩みなどを聞きながら、信頼関係を作っていきます。復帰が見えてきたら、復帰支援のプログラムを作成し、復帰後の業務内容や勤務時間などを検討します。まずは短時間勤務とし、業務内容も比較的軽いものにするとよいでしょう。休職者の上司や周囲の従業員とも話をして、協力してもらえるように調整してください。
支援内容がより具体的にイメージできるように、休職者の職場復帰支援の事例を下記のとおり紹介します。
【休職者の職場復帰支援の事例】
ある大規模外食産業では単に職場復帰を目的とするのではなく、復帰後にスムーズな形で業務に適応できるよう、包括的な支援体制を整備しています。
具体的にはメンタルヘルス不調による休業者の職場復帰支援として、産業医による面談の前に、本部人事担当者や保健師による事前面談を実施。復帰可能と判断された場合には、人事担当者が本人の体調や不安点を丁寧にヒアリングし、復帰予定職場の上司とも連携していきます。
上記のような支援を進めることで、復帰者が安心して職場に戻れるようになるだけではなく、復帰後の再発防止も図れます。復帰後についても、定期的に相談に乗ったり、勤務状況を確認したりして、安心して働けるようなフォローアップを継続しましょう。休職者本人だけでなく、周囲の従業員にも状況を確認することが大事です。
産業保健師のメンタルヘルス対策を強化するために必要なスキル

メンタルヘルス不調者をサポートしたいと思っても、どのようなサポートがベストなのかは難しい課題でしょう。「メンタルヘルス不調」といってもそれぞれ原因や状況は異なるため、一様な対応では意味がありません。
企業のメンタルヘルス対策を強化するには、従業員一人ひとりに寄り添った対応が大切です。そのためには、メンタルヘルスに関する知識や各部署とのコーディネートスキルなどが必要になります。
それらのスキルに加えて、特に必要となるのは傾聴や共感などのコミュニケーションスキルです。具体的にどういった場面で必要になるかについて、下記の事例でみていきましょう。
【Aさんの対応事例】
大手IT企業のAさんは、担当プロジェクトの締め切り期日のプレッシャーによって不眠に悩んでいました。
産業保健師は、批判せずにAさんの話を丁寧に聞いたうえで、「締め切りのプレッシャーは大変ですね」と共感。このような傾聴と共感によって、Aさんは安心して自分の状況を話せるようになり、産業保健師からの睡眠改善策や業務調整の提案を受け入れやすくなりました。
結果として、Aさんはメンタルヘルスの不調を改善できたため、休職することなく業務を続けられました。
メンタル不調者の状況を改善するために、否定や批判を避けたうえで、従業員の不安に寄り添って対応するコミュニケーションスキルが産業保健師には求められます。
また、メンタルヘルスの不調者を支援するために役立つ資格として「産業カウンセラー」があります。従業員のストレスや悩みを改善へと導き、健全なメンタルヘルスを維持できるよう必要なサポートについて学ぶ資格です。日本産業カウンセラー協会の講座を受講し、試験に合格すると資格を得られます。メンタルヘルス対策を知るにも有益なため、ぜひ取得を検討してみてください。
その他にも、産業保健師を対象とした研修会などが開催されています。企業外の環境に触れることで得られるものも大きいため、参加してみるとよいでしょう。
アポプラス保健師でも、保健師として頑張る人向けの研修「アポプラス保健師シャイン研修」を実施しています。今の働き方に自信をつけたい方や、仕事のノウハウを学びたい方はぜひ参加してみてください。
また、産業保健師に求められる資格や研修については、以下の記事も参考にしてください。
本記事では、産業保健師のスキルアップに役立つ資格4選を紹介し、キャリアにつながる選び方や、資格を取得するメリットも解説します。
産業保健師としてよりよい職場で働くには?

産業保健師の職場環境は、働く企業の業種によっても異なります。自分が納得できてやりがいを感じられるような職場で働くためにも、企業の事業内容について調べておきましょう。
もちろん、勤務時間や休日などの確認も大切です。産業保健師の職場は残業や土日出勤が少ないと言われますが、企業の勤務形態によっては残業や土日出勤もあります。いろいろな企業の情報をチェックしたうえで、働く職場を決定してください。
企業ごとの産業保健師の役割の違い
企業の業種ごとに、産業保健師が果たす役割も少し違います。たとえば、製造業の場合には怪我をしやすかったり、重たいものを運ぶために腰痛になりやすかったり、化学物質を扱うために中毒のリスクがあったりします。産業保健師は、これらの問題への対応を迫られることが多いでしょう。
それに対してIT業界では、デスクワークのために運動不足や腰痛、そしてリモートワークが増えたことによるメンタルヘルス不調などの問題が多い傾向です。そのため、産業保健師はこれらの解決に向けて対応します。
転職先に迷っている方は、以下の記事も参考にするとよいでしょう。
本記事では、行政保健師と産業保健師について、年収や仕事内容などの特徴や違いを詳しく解説していきます。
自分に合った職場を見つけるためのポイント
自分に合った職場を見つけるには、企業の求人情報を幅広くチェックし比較することが大切です。そのためには、ハローワークだけでなく人材紹介サービスなども利用してみるとよいでしょう。
中でもアポプラス保健師なら、さまざまな企業の求人情報に出会えるだけでなく、転職活動に必要なサポートも受けられます。どのように転職活動をすればいいのかわからなくて不安を感じている方は、「キャリアサポート無料登録フォーム」から気軽にお問い合わせください。
まとめ|メンタルヘルス対策は産業保健師の重要な役割の一つ
従業員が心身ともに健康で前向きに仕事に取り組むためには、メンタルヘルス対策が欠かせません。メンタルヘルス不調が続くとやがて仕事に支障をきたし、ひいては企業全体の業績にも影響してきます。
メンタルヘルス対策は、産業保健師が果たすべき役割の中でも大変重要なものです。日頃から従業員と信頼関係を築くよう心がけ、気軽に相談してもらえる環境を作っていきましょう。
保健師専門の転職サポート!32年の実績!
転職サポートに登録(無料)【新着】お役立ちブログ
- 2025年11月17日 産業保健師は未経験からでも始められる!キャリアチェンジ完全ガイド
- 2025年11月17日 【2025年最新版】保健師・看護師の平均年収を徹底解説|年代・地域別の違いと収入アップ術
- 2025年11月17日 保健師はフルリモート勤務できる?求人の実情と応募条件・働き方を解説
- 2025年10月20日 産業保健師の転職はエージェント活用で差がつく!未経験でも安心の理由と賢い使い方
- 2025年08月28日 【30代で産業保健師に】未経験からでも目指せる?転職を成功に導く準備とポイント